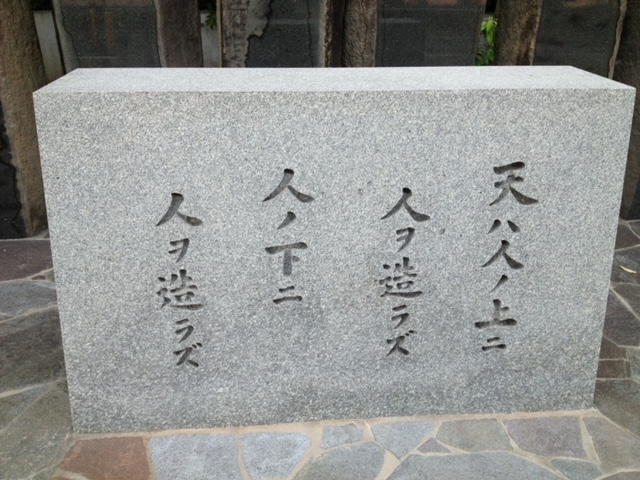慶應義塾大学商学部教授
清水聰
消費者行動論、マーケティング論
慶應義塾大学商学部卒、同大学大学院修士課程、博士課程卒。博士(商学)。明治学院大学経済学部専任講師、助教授、教授を経て、2009年より現職。消費者行動の理論に基づき、マーケティング戦略の策定・実証を行っている。「日本初のマーケティング」、「戦略的消費者行動論」(いずれも千倉書房:単著)、New Consumer Behavior Theories from Japan (Springer:単著)。
消費者行動の理論を用いたマーケティング戦略の解明
慶應義塾大学商学部教授 清水聰
私の専門は、企業の行うマーケティング戦略を、消費者の行動に関するさまざまな理論と、その消費者の行動や意識に関するデータ分析を用いて解明する研究である。消費者を対象としたマーケティング戦略を企業が実行するには、自社の商品やサービスが消費者に受容されるのかどうかを知る必要がある。その際、大事になるのは、実際に多くの消費者と接している、いわゆる現場の人の感覚的な知見だ。ただその感覚をきちんと数値化し客観的に提案できなければ、企業は踏み出せない。営利企業である以上、「何となくこの方向」、では不十分で、利益がきちんと出るのか、客観的な裏付けが必要なためである。このため消費者の意識やニーズの数値化と、その数値の分析がマーケティング戦略の実行には重要である。
この分野の研究、当初はアンケートを用いて消費者の考え方や意識を調査し、そのデータを分析して進められており、社会学や心理学をバックグラウンドに持つ研究者が活躍していた。具体的には、心理学や社会学で使われる各種尺度を、5段階(大変そう思う、そう思う、どちらでもない、そう思わない、全くそう思わない)で消費者に回答してもらい、その数値を分析して戦略を考えていく方法だ。近年では、個人の意識やニーズが、その人個人の状況だけではなく、社会情勢の変化、たとえばサステナブルなどの影響を大きく受けることが明らかになっている。個人の欲求もそうだが、社会に目を向けた行動を、人々がとるようになってきたと言える。
小売業でPOSシステムが導入された1980年代以降は、消費者の購買履歴データが大量に、容易に収集できるようになったことと、数理統計学の各種手法がコンピュータの急速な発展で利用可能になったため、主としてデータ分析を専門とする、理系の研究者が研究の最前線に登場してきた。過去の購買履歴は、その消費者の買い方の「癖」を示している客観的事実であるため、何を買うのか、何を好むのかを予測する際の予測精度が、アンケートから得られた主観的な意識データよりも遥かに高いためである。現在では、ビッグデータと呼ばれる、消費者の購買履歴だけではなく、ネット上での買い物に至るまでのクリックストリームデータや、購買後の感想をSNSに発信するデータなどが紐づけられ、消費者に関する客観的データがリッチになってきている。AIの発展も加わり、この高度な数式を用いた消費者データの分析とマーケティング戦略への応用は、しばらく続きそうだ。
その一方で、これだけ多くの要因が消費者の好みや選択に影響する状況では、企業の行うアクションの効果を正確に測定するには、外部の多くの要因をコントロールすることが必要になってくる。このため、実験室や、より大規模な実験店舗を用いた研究も多く行われている。実験素材を複数用意し、コントロールされた状況の中で、その素材感の差をアンケートで測定するのがオーソドックスな方法だが、近年ではより客観的なデータの必要性から、被験者の目の動きを測定するアイトラッキングや、脳波を測定する機材など、消費者の生体反応を用いた試みがなされている。ウェラブル端末が普及している現在、これら生体反応のデータは、企業のマーケティング戦略を考えていく上で、重要になると考えられる。
このように、消費者の理論とそのデータを用いたマーケティング戦略は、データの進化とともに発展してきたが、現在、また今後問題となりそうなことをいくつか指摘しておきたい。
一つは、データの管理と分析者の倫理観の問題である。オンラインで買物をした際、自分の好みに合致した商品が推奨され、タイパが高く便利と感じる反面、自分の好みがここまで把握されて恐ろしい、とも感じた経験は誰しもあるだろう。企業側は、消費者の買物の利便性を高め自社を贔屓にしてもらう意図で、ビッグデータやアンケート、実験を通じた結果をもとに推奨を行っているわけだが、自分の行動が詳らかになることへの抵抗が強いことも確かだ。日本では個人情報保護法が施行され、個人の情報を守る動きがある一方で、マイナンバー制度により、個人の各種データがどんどん一元管理される方向にある。この2つの相矛盾した社会の変化の中で試されるのが、データの管理と分析者・企業の倫理観である。ライバルの研究者に勝つには、どうしても有用なデータを分析する必要があるが、そこにどこまで倫理観をもって進めるのかは、研究者として考えなければならない点だろう。
二つめの課題は、アンケート調査の精度の問題である。購買履歴をはじめとするビッグデータは、消費者の行動の客観的記録であり、非常に有用ではあるが、そこにたどり着いた理由は、データから推測はできるものの、結局は消費者にアンケートしなければわからない。その二つを組み合わせることで、より意味のあるデータになる。但し、近年のインターネット調査の普及から、被験者である消費者がアンケート慣れしており質問者の意図を忖度して回答するケースが非常に増えている。本当にきちんとデータが把握できているのか。それをきちんと識別して研究に用いる必要が出てきている。
三つめの課題は、先進国での急速な高齢化である。今までのマーケティング戦略は、買物に積極的な、若い人、若いマインドを持った消費者をターゲットとして行われてきた。若い人の方が、利幅の大きい新製品や新サービスに関心を持ち、飛びつく可能性が高いからである。しかし国民の25%以上が高齢者で、少子高齢化が進む日本では、若い人だけをターゲットとしては先細りになるのは明白だ。加えて高齢者の数がこれだけ増えてくると、「高齢者」と一括りで捉えていくのは無理がある。今まで欧米のマーケティング理論をベースに消費者を捉え、マーケティング戦略を考えてきたが、ターゲットが変化してきている以上、日本独自の理論を構築し、世界に発信するような、研究者の姿勢の変化が求められる。
以上、私の専門分野についてその概要を示してきたが、最後、この状況の中で、現在私が主として行っている研究について簡単に紹介したい。一つは先端層の研究で、この人たちの行動を観察することで、新製品や新サービスの定着度合いを測定する研究だ。高度な分析手法を駆使しなくても予測精度が高く、企業にも好評である。次に、消費者の生体反応を用いた、消費者の商品を手に取るまでの行動の研究も行っている。新しいテクノロジーを応用して、消費者の気持ちの変化をより客観的に捉えることが目的で、アンケート調査の弊害を取り除けるのではと期待している。最後、加齢によって生じる買い物行動の変化も、長期にわたる購買履歴データから分析している。これにより、加齢による購買行動の変化がわかり、一体何がトリガーになったのかを、今、探っているところだ。
このように、消費者を対象とした企業のマーケティング戦略の研究では、社会の変化やデータの変化に応じて、さまざまな理論を組み合わせ、臨機応変に対応していく必要がある。答えや手法が一つに定められないのが、大変でもあり、醍醐味でもある。