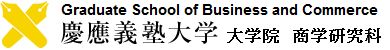修士課程 [入学定員80名]
■商学研究科の基本理念
慶應義塾大学商学研究科の研究教育に対する基本理念は、創立者の「実学の精神」を継承し、理論と実証を通じて現代のグローバルな産業社会を把握し、進歩と変革の方向を洞察することにあります。「実学の精神」とは、経済社会を把握するための実証精神に支えられた、既成の権威や価値にとらわれないものの見方、現実の中から将来を見据え、自らの価値を創造する態度を称するものです。商学研究科は1961(昭和36)年に開設されて以来、一貫してこの基本理念のもとでカリキュラムを構築し、教育を行ってきました。そこでは、制度についての表面的な知識の習得にとどまることなく、常にその背後にある、社会を動かす基本的な構造的メカニズムを理解できるよう工夫が凝らされてきました。
社会が安定しているときは、制度が果たしている基本的な役割などをそれほど意識する必要はありません。制度についての表面的知識さえあれば、あるいは他人の行動を模倣さえすれば、十分に対応することができます。しかし、社会が大きな変化にみまわれたときには、小手先の知識だけでは役立ちません。制度や慣行、人々の行動について、理論に裏打ちされた構造を理解し、それらの生きた結びつきを知っておく必要があります。
日本社会は今、まさにこのような状況にあります。社会の変化が激しければ激しいほど、表面的な知識はすぐに陳腐化し使えなくなってしまいます。今後の社会をリードしていく指導者には、高度で専門的な知識とともに、基本的な社会構造を理解し、将来を洞察する力が求められるのです。
■商学研究科教育の目的と特徴
商学研究科では、基礎から応用、演習、そして修士論文作成指導に至る体系的なカリキュラムが組まれています。修士課程の院生は導入科目としてビジネスエコノミクスが選択必修科目となっています。これは各専門分野を深く理解するためには、企業や消費者の経済行動についての基礎的理解を得ることが必要であるからです。本研究科では、商業学、経営学、会計学のほか、金融・証券論、保険論、交通・公共政策・産業組織論、計量経済学、国際経済学、産業史・経営史、産業関係論などの多様な分野の教授陣が充実していますが、それぞれの分野では基礎科目から専門科目までを体系的に学べるカリキュラムとなっており、修士課程の院生は特定の分野に偏ることなく、幅広い知識を基礎から応用まで学ぶことができます。基礎科目は大学院生1人ひとりの多様な進路目標に応えることができるよう、多様な授業科目を設置しています。例えばファイナンス、統計学基礎理論、経済数学基礎理論、ミクロ・マーケティング論、マクロ・マーケティング論、産業組織論、リスクマネジメント論等の多様な授業科目を設置し、企業の財務部門、経営企画部門、公的組織、研究機関、コンサルティング会社等への就職希望者にも対応した授業を行っています。これら導入科目と基礎科目を学んだ上で、専門科目では各分野の応用について深耕を行っていきます。また日本語の授業だけではなく、英語で行われる授業も多く用意していますので、将来の留学や国際的な学会での報告にも資することができます。さらに修士論文指導のための演習科目および合同演習科目が設置されています。
商学研究科では修士論文の作成が課されており、2 年間の修士課程での研究活動の成果が評価されます。修士論文では、新しい研究上の成果を出すことはもちろんですが、研究論文として形式面での要件の整備など、研究者として必要な素養を学ぶことになります。
■募集定員と入学の方法
募集定員は、80 名です。入学の方法としては、一般入試とAO 入試(一定の要件を充足する者に対し、書類と面接で入学の許可の判定をすること)、および留学生入試があります。また、本学商学部の成績優秀者には、3年次に一般入試を受験することができます。このことにより、3年生終了時点で大学院に飛び級で入学することもできます。各入試制度の詳細(出願資格等)については、各入試要項を参照してください。
■取得学位と修了必要単位数・修了要件、および修士論文の審査基準
取得学位は「修士(商学)」です。修了必要単位数は32 単位です。このうち導入科目のビジネスエコノミクスⅠ・Ⅱ、Business EconomicsⅠ・Ⅱから1科目以上(2 単位以上)、演習科目から4科目以上(8 単位以上)の履修が必要です。
また、2年間以上商学研究科修士課程に在学し、学位論文(修士論文)の審査ならびに最終試験に合格することが修了要件となっています。学位論文(修士論文)の審査基準については以下の「修士論文審査に関する内規」(抜粋)を参照してください。
修士論文審査に関する内規(抜粋)
慶應義塾大学大学院商学研究科における修士学位論文審査の基準および方法を以下のように定める。
1.審査基準修士学位論文は、以下の点を考慮し審査する。
①表現が明確で構成が論理的であること。
②当該分野の過去の研究成果が十分に参酌され、論文の課題と成果の学術的な位置づけが明確であること。
③学術論文として適切な形式的要件を備えていること。
④最終試験における質疑に的確に応答できること。
■研究指導計画(研究指導の方法およびスケジュール)
・入学時に決定した指導教員が修士論文執筆まで指導します。・履修にあたっては、指導教員の担当科目のみならず幅広い科目を履修し、他の教員からも積極的に指導を受けるよう心掛けてください。
・以下は修士課程2年間の標準的な研究指導スケジュールです。詳細入学後すぐに指導教員と相談してください。
| 学年 | 時期 | 研究内容および指導方法等 |
|---|---|---|
| 1年次 | 4月~6月 | 指導教員の決定、履修相談 研究テーマの決定、指導教員による研究計画作成指導、演習授業での研究計画発表 |
| 7月~9月 | 研究計画の実行 | |
| 10月~12月 | 演習授業での中間報告 | |
| 1月~3月 | 指導教員による研究進捗状況の確認と計画変更の検討 | |
| 2年次 | 4~6月 | 研究計画の実行、演習授業での中間報告 |
| 7月~9月 | 研究計画の実行、指導教員による論文執筆指導 | |
| 10月~12月 | 指導教員と相談の上で修士論文タイトルの提出、主査副査の決定 演習授業での研究成果報告 |
|
| 1月~2月 | 修士論文の提出、最終試験(論文審査) |
■ジョイントディグリー制度
今日の社会では幅広い知識と柔軟な思考力、加えて的確な判断力を兼ね備えた人材が強く求められています。こうした要請に応えることができるように、本研究科の修士課程では2010(平成22)年度から、文学研究科、経済学研究科、法学研究科との間でジョイントディグリー制度を開始しました。ジョイントディグリーとは、一定期間で複数の学位を取得できる制度ですが、この制度を利用すれば、2 年ないし3 年間で2 つの修士学位(商学と文学、商学と経済学、商学と法学)を取得することができます。進路選択の幅がさらに広がることにもなります。
短期間で2 つの学位を取得できるのは、最初に学ぶ研究科の修士課程在学中に、2 番目に学ぶ修士課程の単位を最大12 単位まで先行して取得できる上、最初の修士課程修了のために取得した単位を最大10 単位まで2 番目の修士課程の修了単位に充てることができるという優遇措置があるためです。
ジョイントディグリーの取得希望者には、一般入試とは別の入学試験が行われます。応募できるのは、最初の研究科の第1 学年または第2 学年の在学者で、当該年度末に修了見込みで、かつ2 番目の研究科でのジョイントディグリー取得を希望する学生です。ただし、文学研究科にはジョイントディグリー制度の対象に含まれない専攻もあります。詳細については、現在所属する研究科担当窓口の学生部担当者にお問い合わせください。