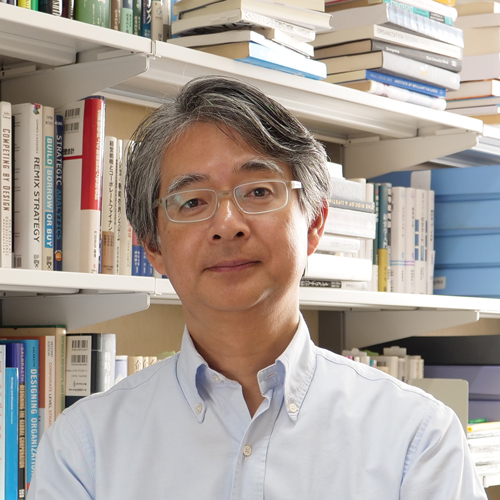
慶應義塾大学商学部教授
牛島辰男
経営戦略、企業財務
三菱総合研所研究員、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授を経て2015年より現職。Ph.D. (Management)。主な著書に『企業戦略論:構造をデザインする』(2022)。Financial Management、Journal of Banking & Finance、Research Policy、Journal of the Japanese and International Economies、Journal of Economics and Business 等に論文。
企業の多角化と成果の研究
慶應義塾大学商学部教授 牛島辰男
研究の領域と目的
私が主に研究しているのは、日本企業による事業の多角化です。多角化とは企業が複数の事業を持つことを指し、多角化している企業を多角化企業と呼びます(複合企業(コングロマリット)と表現されることもあります)。大企業は多角化を積極的に進め、広範な事業を持っていることが珍しくありません。
多角化には、成長や資源活用の機会が増えるといった利点があります。一方、多角化により企業の組織は大きく、複雑になります。戦略を定め、実行することも、1つの事業に集中している方が容易です。ゆえに、多角化が企業業績(パフォーマンス)の向上に結び付くとは限りません。私の研究は日本企業による多角化の実態とパフォーマンス(特に企業価値)との関係を分析し、企業が多角化を進めていく上での課題を明らかにすることを目的とします。その1つの成果が、コングロマリット・ディスカウントと呼ばれる現象を分析したUshijima (2016)です。この論文は、助走期間を含めると10年以上の時間を経て生まれていますので、その経緯をご紹介します。
きっかけは日本企業の低迷
私が多角化に関心を持ったのは、大学院の修士課程を修了し、民間のシンクタンクに就職してからです。当時は、多くの日本企業がバブル崩壊の影響に苦しみ、ずるずると業績を低下させていました。何が原因なのかと考えた時に、多角化マネジメントの失敗が1つの候補として浮かんだのです。過去に始めた事業が成果を生み出していないにもかかわらず、撤退などの対応が十分に行われず、問題を深刻化させていく企業が多く見られためです。そうした中で、米国の経営大学院(ビジネススクール)の博士課程に留学し、経営戦略を学ぶ機会を得ました。
米国では、重要な発見がありました。コングロマリット・ディスカウントという耳慣れない現象が注目を集めており、その分析を財務(ファイナンス)の研究者が主導していたことです。そこで私は、ファイナンス分野(特にコーポレート・ファイナンス)を強く意識しながら、経営学を学ぶことになりました。残念な発見もありました。事業セグメント情報と呼ばれる基礎データが、日本では開示が始まったばかりだったため、米国の最先端の研究を同じように行うことは難しかったのです。ただ、多角化と同様に企業を複雑化させる国際化については良いデータがありました。そこで、博士論文では日本企業の国際化と企業価値の関係を分析しました。
多角化の分析をはじめる
2003年に帰国しても、データの制約は解消しません。日本企業のセグメント情報の開示は2000年からであり、本格的な研究には少なくとも10年程度のデータが必要です。データの蓄積ができるまで、2つの形で研究を進めました。
第1はセグメント情報を用いない分析です。セグメントデータがないということは、2000年以前は日本企業が多角化していなかったということでも、その研究がなかったということでもありません。例えば、吉原他(1981)は大企業118社の多角化の度合いとタイプを丹念に把握し、業績との関係を分析しています。そこで、青山学院大学の福井義高教授と共同で、この研究との連続性を維持しつつ、分析期間を延長し、手法もアップデートした分析を行いました(Fukui and Ushijima, 2007)。非常に手間のかかる研究でしたが、多角化を研究していくための基礎ができました。
第2は、リストラクチャリング(事業再編)の研究です。例えば、Ushijima(2010)では事業統合に注目しました。事業統合は同じ事業を持つ企業同士がその事業を合弁会社にまとめ、共同で運営するため、部分合併ともいえるリストラクチャリングです。企業全体の合併を行う企業に比べると、事業統合を行う企業は多角化度が顕著に高いなど、興味深い発見が多くありました。
コングロマリット・ディスカウントの検証
そうこうしているうちに、データの蓄積も進み、コングロマリット・ディスカウントの検証ができるようになりました。この現象は、多角化企業の企業価値(株式の時価総額+負債)が、同じ産業の専業企業よりも低くなる傾向を指します。計測してみると、日本の多角化企業にも確かにディスカウントが見られました。ただ、これだけでは国際的に通用する論文にはなりません。世界の研究は進歩していたからです。
1つの進歩は、解釈です。コングロマリット・ディスカウントは、多角化が企業価値を低める証拠としばしば見なされますが、実はその意味は明確ではありません。1つの理由は、多角化が企業の選択であること(内生性)です。多角化した企業には、既存事業での成長機会が乏しいなど、専業企業に比べて企業価値を低める別の要因があるのかもしれません。だとすると、多角化自体が企業価値を向上させたとしても、その要因ゆえに多角化企業がディスカウントされることはありえます。米国企業については、内生性を考慮すると、ディスカウントは消えてしまうという研究もありました。そこで、内生性を踏まえた推計を行いましたが、日本の多角化企業のディスカウントは消えることなく、残りました。
組織の影響にも注目しました。多角化により企業の組織が変化することは、早くから知られています(Chandler, 1962)。だとすると、ディスカウントは多角化で事業の幅が広がることよりも、複雑化した組織に由来するのかもしれません。組織は体系的な把握が難しい要因です。しかしながら、組織構造の1つの側面であるグループ構造は、日本では測定が比較的容易です。日本の上場企業は、グループ全体(連結)と親会社単体の双方の情報を開示するため、企業内で親会社の外に組織されている活動のウェイトがつかみやすいのです。多角化企業では、このウェイトが高くなる傾向があります。そこで、グループ構造を考慮した推計を行いましたが、コングロマリット・ディスカウントは変わらずに観測されました。ディスカウントはかなりの程度、多角化そのものに由来すると言えそうです。これらの結果をまとめたのがUshijima (2016)です。
現在取り組んでいる課題
この論文で研究に1つの区切りがつきましたが、終わりではありません。現在の主なテーマは、多角化の価値の変動と分散です。コングロマリット・ディスカウントの大きさは時期によって変わります。この変動が生じる仕組みを、資本市場の役割に注目して、分析しています。一方、多角化の価値は企業によっても異なります。多くの企業を平均した姿がディスカウントであっても、プレミアム(価値の向上)を実現している企業も多く存在するのです。こうした企業間の違い(分散)が生じる理由を、事業の組み合わせとしての企業の特性に注目しながら、考察しています。どちらも簡単な課題ではありませんが、研究を通じて、より良い多角化マネジメントに少しでも資することができればと考えています。
参考文献
吉原英樹・佐久間昭光・伊丹敬之・加護野忠男 (1981)『日本企業の多角化戦略: 経営資源アプローチ』日本経済新聞社
Chandler, A.D. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise, MIT Press.
Fukui, Y. & Ushijima, T. (2007). Corporate diversification, performance, and restructuring in the largest Japanese manufacturers, Journal of the Japanese and International Economies 21, 303-323.
Ushijima, T. (2010). Understanding partial mergers in Japan, Journal of Banking & Finance 34, 2941-2953.
Ushijima, T. (2016). Diversification, organization, and value of the firm, Financial Management 45, 467-499.