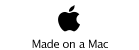Taj多事
2011
今日は,DelhiのMahavir EncloveにあるSulabh Internationalを訪問。インドには,長い歴史をもったカーストという階級制度がある。それは,バラモン(司祭),クシャトリア(王族,武士),バイシャ(平民),シュードラ(隷属民)の4つのヴァルナからなるが,統治の過程の中で不可触民という第5の最低の階級が形成された。各ヴァルナは,通婚,水のやり取り,共食の範囲を限定するジャーティと呼ばれる職業集団で細分化されているが,シュードラのうち排泄,死,血など汚れたものに携わるジャーティに属する人たちが不可触民として差別的な扱いを受けてきた。イギリスから独立後の1950年に発布されたインド憲法の17条は,あらゆる不可触性を禁止し,不可触民は指定カーストとしてさまざまな優遇措置などを受けられるようになったが,特に農村部においては不可触性は残ったままであるのが実情である。不可触民の中でも,人間の糞尿を手で回収し,それを一斗缶のような器に詰め,その器を頭の上に載せて処分場まで運ぶことを生業にするマニュアル・スカベンジャーと呼ばれる人たちは,不可触民中の不可触民とされ,現在においてもあってはならない差別を受けている。彼女たちは,何の防護もなく無差別に人の糞尿に接するわけであるから,常に感染症のリスクに曝されている。
Sulabh Internationalを創設したBindeshwar Pathak博士は,スカベンジャーを必要とする乾式掘り込み便所をなくして,スカベンジャーを失業させれば,スカベンジャーを最低の仕事から解放することができると考えた。Dr. Pathakのイノベーションは,乾式掘り込み便所を壊して根絶やしにするのではなく,人の手による清掃が不必要で,だれもが使うことのできる低コストのトイレで代替させることにある。そして,スカベンジャーを失業させると同時に,他の職に就かせるための教育と職業訓練の場を提供することも忘れない。ブラーミン(バラモン)であるDr. Pathakが,このようなことを発想し,実行したことがインドにおいては考えられないことなのである。
Sulabh InternationalのMs. Anita Jhaとのやりとりで,本日は10:00に始まるお祈りの朝礼から参加することになっている。今日はセナさんが同行する予定であったが,われわれがJaipurにいる間にセナさんの顔に出来物のようなものができ,体調がいまひとつということで欠席。セナさんが同行すれば彼の車でKarol Baghまで行く予定であったが,7:30にSmile Innを出発して学生の滞在するKarol BaghのBharat Palaceへメトロと徒歩で向かう。Sulabh InternationalのあるMahavir Encloveは,Indira Gandhi International Air Portの近くにあるので,渋滞を見越して早めに出発したが,さほどの渋滞はなく予定よりすいぶんと早く9:15に到着。
ゲート番もわれわれの訪問をわかっていてすぐに会議室に通された。ほどなくMr. Gaurav Chandraが現れる。彼には2010年1月に一人でここを訪問したときにお世話になった(2010年1月2日のTaj多事参照)。そのときに「今日伺った話を日本の学生に伝えなきゃいけないし,機会があればぜひ学生を連れてきたいと思う」と小生が言ったのに対して,彼が「Most welcome」だと言ってくれた。今回の訪問においても彼に最初のコンタクトをとり,彼がSenior Vice PresidentのMs. Anita Jhaに取り次いでくれて,実現したのである。
総勢16名が大きなグランド・テーブルにつくと,GauravとこのあとSulabh式便所の解説をしてくれる女性から今日のスケジュールなどを聞いて,雑談をかわす。ほどなく,今回のコーディネートをしていただいたAnita女史が挨拶に来てくれた。するとDr. Pathakが登場。これは全く想像していなかったことで,TERIであればDr. Pachauriが出てきたようなもの,もっとわかりやすく言えば,慶應でいえば塾長が出席してくれたに等しい。Dr. Pathakは,グランド・テーブルの中央に腰掛け,「Welcome」の挨拶に続いて,Sulabh Internationalのコンセプトや目的についてのお話をいただいた。小生が,昨日Amber Palaceで撮ったスカベンジャーと思われる写真をiPadでお見せし,彼女たちがAmber Palaceの公衆トイレで働いていた話をすると,「確かに彼女たちは,スカベンジャーにちがいない。Amber Palceではまだそんなことをしているのか」と少々がっかりの様子であった。
10時になったところでAnitaさんの先導で朝礼に向かう。AnitaさんとDr. Pathakを先頭に講堂へ案内される。そこには,マニュアル・スカベンジャーの女性達,Sulabh Public Schoolで学ぶ子供達,そしてSulabh Internationalのスタッフが一同に会し,整列している。われわれは壇上に案内され小生を中心にして一列に,Sulabhの方々と向き合って並んだ。お祈りの歌が始まる。みな目を瞑り,胸の前で合掌している。われわれも壇上で同じようする。
お祈りが終わるとAnitaさんが,われわれのことを紹介した。さらにAnitaさんが小生を筆頭に一人一人の名前を呼び上げる。われわれは,名前が呼ばれると一歩前へ進んで会釈。次には,Dr.Pathakに一人ずつ招かれ,Dr. Pathak自らが花輪をかけてくださり,アシスタントの女性がストールを肩へかけてくれた。このような光景は,何度か目にした。たとえば,Delhiで開催された古典舞踏会で,観劇に来ていたDelhiのCM(Chief Minister: 知事)が壇上に招かれ,同じように花輪とストールで歓迎された。このような丁重な歓迎にどのように答えてよいのか,少々緊張気味である。
歓迎の式が終わると,生徒二人が前に出て,感謝の気持ちと今日も一日頑張りましょうというメッセージを朝礼に参加している全員に英語で読み上げる。最後に,Dr.Pathakが「A Hymn to Harmony」という最初と最後を「Let's all come together and build a happy Sulabh world.」で締めくくる詩を朗読して,あいさつをする。あいさつの最後は,「技術は,社会の中で虐げられている人たちを救うことができる」という言葉で締めくくられた。小生の方から何かあるかとDr.Pathakから促されたのだが,このような神聖な朝礼で何を話すのかパッとは思いつかず,お断りしてしまった。少しでも話しておけばよかったと,この後ずーっと後悔していた。次回来るときには,あらかじめ準備して,ぜひお話させていただこう。最後にスカベンジャーの女性たち,それにDr. Pathakと記念撮影をして。Sulabh Public Schoolへと向かった。
Sulabh Public Schoolは,Sulabh Internationalの本部がある複合施設の隣にある。トイレ博物館の前からいったん外に出て学校に入る。
現在,Sulabh Public Schoolでは1年生から10年生までの380人が勉強している。うち60%がスカベンジャー家計の子供たちで,その他40%は普通の家計の子供たちである。スカベンジャー家計の子供たちの授業料,文房具,制服はすべて無償である。授業は全て英語で行われ,言葉の教育として英語,ヒンディーのほかに,不可触民への教育を禁じられてきたサンスクリットも教えている。憲法で不可触性が禁じられているので,不可触民家計の子供達もGovernment Schoolで勉強する権利を持つ。しかし,経済的な理由でWorking Childrenになり就学しない子供が膨大にいることはAWCのところで述べた。ましてや不可触民家計にとって質の高い教育を提供するPublic Schoolへ子供通わせることなどとてもできない。Sulabh Public Schollの特徴は,スカベンジャー家計の子供たちに質の高い教育を提供し,さらに質の高い教育を受けられる普通の家計の子供たちと同化させることにより,普通家計の子供たちのみならず,スカベンジャーの子供たち自身に同じ人間であるという尊厳を回復させようと試みていることである。1992年にこの学校を開校した当初はこのようなDr. Pathakのやり方に批判も少なくなかったが,いまでは地域住民もSulabhの考え方に賛同しているということだ。
最初にサンスクリットを勉強している10年生の教室に案内された。そこでも生徒の一人がわれわれに英語で挨拶をしてくれた。何か生徒達に一言と求められたので,「私たちは日本で,どうしたら貧しい人たちと豊かな人たちのギャップを縮めることができるかという課題を経済学的に研究しています。インドへは,そのギャップの現実を観るためにやってきました。今日は,みなさんの学校を見学させていただいて,たくさんのことを学びたいと思います」と朝礼のときの後悔もあったので,このように話させていただいた。
Sulabh Public Schoolのもう一つの柱は,Vocational Training,つまり職業訓練である。Sulabh式トイレの普及によってスカベンジャーが失業したあとに,彼女達が自立できるように職業訓練も施すのである。設置されている技能はHPPIのAWCとほぼ同じで,女性向けにCutting & Sowing,Beauty Care,男性向けにAudio-Visual Repair,Electrical Equipment(電気の配線や修理),男女を問わずTyping,Computerなどがある。いずれも1年間のコースで,終了後にはITI(India Training Institutes)による認定を得ることができる。この点は,AWCの3ヶ月コースとの大きな違いで,訓練後の就職をより確実にしている。Cutting & Sowingを終えた人は,Embroidery(刺繍)とDress Designingに進んで,自らがデザインした洋服を世に出せるまでになるそうだ。ほぼ上に述べた順番で教室を見せていただいた。
Sulabh Public Shcollのもう一つのイノベーションは,初潮を迎えた女の子たちに生理用品を自作させていることである。当初は,自動販売機を設け,そこで生理用品を買わせていたそうだ。ところがスカベンジャー家計の子供たちは,それを使わず,自分たちの用意した布を使って非常に不衛生な状態であったという。その状況を改善させるために,商品を無償で配布するのではなく,生理用品にどれだけ衛生上の気を配らなければならないかを気づかせるために,殺菌設備,脱脂綿の圧縮機など一連の設備を取り揃え,自作させているのだ。その工程を二人の女子生徒が英語で説明してくれた。自作にはある程度の時間が必要で,緊急用に自動販売機はいまでも設置されている。
Sulabh Public Schoolを離れ複合施設に戻り,次にトイレ博物館を見学させていただく。ここからは,Dr. Pathakの言う技術の部分である。前回訪問したときにガイドしてくれた青年も中にいたが,今日はベテランのガイドがわれわれを案内してくれる。前回来たときと展示物が変わっているわけではないのだが,今年のガイドさんはユーモア交じりに解説してくれるのでとても楽しい。本を積み上げた形のトイレがある。「こいつは,フランス人が読書好きのイギリス人を尻の下に敷くためにこさえたものさ」なんてユーモアたっぷりに話してくれる。ただ話の筋は通っている。そもそも,現代風の衛生的な水洗トイレと汚水処理の仕組みは,紀元前2500年のインダス文明におけるハラッパ,モヘンジョダロの遺跡から発見されている。しかし,インダス文明の衰退とともにこのように衛生的なトイレの仕組みも消滅してしまう。博物館には中世ヨーロッパで2階の窓からバケツに入れた糞尿を道路にぶちまけ通行人が逃げ惑う絵が展示されている。1500年代半ばにイギリスのHaringtonが再び水洗トイレを開発するまで,人類は衛生的なトイレの仕組みを忘れていたというのである。それでもHaringtonの水洗トイレが普及するのは18世紀になるまで待たねばならなかった。インドの人々は,インダス文明の衰退以来,いまでも野外排泄をエンジョイしているのである。以上が展示物の解説を交えながらのガイドさんの説明のあらすじだ。
博物館の外へ出たところに最後の展示物がある。高さ2m15cm,幅75cm,厚さ20cmの大物である。これは,2005年から2006年にかけてメキシコ人の芸術家が人糞でつくった身体測定器である。一見したかぎり,これが身体測定器といわれてもよくわからないのであるが,その横にある説明には次のように書いてある。彼らは全部で21体制作したが,その一つがここにある。人糞はNew DelhiとJaipurで集められ,3年間をかけて乾燥させて粘着性のある樹脂を混ぜて固めた。そして制作作業は,スカベンジャーの解放を目指しているSulabh Internationalの全面的な協力得て行われたと。ガイドさんがこの展示物の説明にはとても熱心だったので,ここにも記しておく。
さて,ここでも残念だったのは,ガイドさんが学生達への説明を途中で諦めてしまったことだ。「彼らは英語がわからないのかもしれないけど,そもそも興味がないらしい」「確かに英語には少々問題があるかもしれませんが,興味はあるはずです」「でも,私の話はほとんど聞いていない」と言われてしまった。「ちょっと人数が多過ぎたのかもしれません。申し訳ありません」と言い訳をしたが,申し訳ないやら情けないやらの気持ちで一杯である。なんとか理解しようとしてくらいついて,わからないことを質問しようという気概がほしい。「わからないからいいーやー」というような覚めた気持ちは断ち切ってもらいたい。自分がガイドをしたらどう思うだろうという,相手を思いやる気持ちも持ってほしい。このガイドさんは,われわれへの案内が終わると,Public Schoolへ通じる門から出て行った。きっとわれわれのためだけに来てくれたガイドさんにちがいない・・・
博物館の前には,Sulabh Shauchaiyaと呼ばれるDr. Pathakの着想でSulabh Internationalの技術者たちが開発したスカベンジャーの要らない水洗トイレが展示されている。仕組みはいたって単純である。便器1つと便槽2つで1つのトイレを構成する。便槽は,その大きさに対応して2年周期から40年周期で交互に使われる。たとえば2年ものの場合,2年経っていっぱいになった便槽は閉じられ,もう一つの便槽にその役割をバトンタッチする。もう一つの便層も2年後にはいっぱいになる。そのときには,閉じておいた便層の糞尿は乾燥して堆肥になっているので,それを取り出し肥料として使い,空になった便槽を再び使い始める。
という具合に,糞尿を全て堆肥としてリサイクルして,糞尿として処分する必要のない技術を提供するのがSulabh Shauchaiyaの特徴である。それを容易にかつ確実するために二つの工夫がされている。その一つが便器の角度。試行錯誤の結果得られた現在の便器の角度では,一度に使う水の量が2リットルで済む。われわれが日常用いているトイレでは10リットルほど使っている。これで完全に便が流れると同時に,一部が便器と便槽をつなぐパイプ内に残り,その水が臭いを消し,パイプを衛生的に保つことに役立っている。また,2リットルという少量の水は,便槽に余計な水を貯めないので堆肥の生産がスムーズに行われる。もう一つの工夫は,便槽壁に空けられたいくつもの穴である。ここから有機物がバクテリアによって分解されたときに発生するバイオガスと余計な水分を逃がすことができる。バイオガスについては有効利用できる余地があるから無駄が生じているわけであるが,このおかげでできた堆肥は無臭である。実際に,堆肥を固めたものの臭いを嗅いでみたが,これがもとウンチとは想像もできない。
Sulabh Shauchaiyaにはさまざまなオプションが用意されている。便器を野外に置く場合,便器を取り囲む壁の基本はコンクリートであるが,天然素材の木の枝などで組上げることによりコンクリートの費用を削減できる。便槽の素材についても同じことが言える。また,野外排泄を好むインド人にとっては周囲を完全に壁で囲われてしまうのは不安に感じるようで,天井なしというオプションもある。このように建築素材を工夫することによって,貧しい家計でもSulabh Shauchaiyaを導入することができるような工夫も施されている。
このSulabh Shauchaiyaが120万戸の家屋に設置されている。これによって解放され復権したスカベンジャーは100万人以上にのぼり,スカベンジャーを必要しなくなった町は640にのぼるという。
Sulabh Internationalが運営する複合施設では,Sulabh Shauchaiyaで廃棄していたバイオガスと水も完全に再利用している。ガスは,厨房での調理,電灯,暖房,発電の燃料として消費され,水はフィルタリングすることによって無臭になる。しかし飲料には適さないので,施設内の植物に撒布される。Sulabh Internationalが建設した公衆トイレ,複合施設の数は7500にのぼり,200の施設がバイオガス施設を備えている。
一通りの説明を聞いたわれわれは,質疑応答のために会議室に戻った。再びDr. Pathakが参加して,時間の許すかぎり質問に答えてくれるという。Gaurav氏は,学生たちが英語で質問するのは難しいと判断して,学生たちから日本語で質問を受け付けて,小生から英語で質問をしてはどうかと提案する。学生たちもその方がcomfortableだというので,少々時間をもらって学生たちから質問を受け付ける。スカベンジャー家族の子供たちと普通の家族の子供たちが同じ場所で勉強することに対する批判はないか,職業訓練後の就職に制約はないか,職を得たスカベンジャーたちの生産した生産物に対する忌避感を抱くものはいないのか,学校内における差別的な行動はないのかなど,不可触性に関わる質問が多かった。先に書いたように1992年に開校した当時には様々な問題があったが,今は多くの人がSulabhの考え方に賛同してくれているとうのがDr. Pathakの答えだ(実際にはもっともっと長い)。不可触性に疑問を持った若きDr. Pathakは,不可触民を実際に触ってみたり,寝食をともにすることで何が起きるのかを試してみた。起こったことは,お清めの儀式として祖母から牛の尿を飲まされ,牛の糞を食べされたことだけだった。こういう経験をしているDr. Pathakであるから,自分の意志を貫くために他人がどんな反応をするかなんてことは大した問題ではなかったのだろう。
Sulabh Internationalはその活動資金として政府からの補助や援助団体からの支援金を使っていない。その理由は,いわゆるひも付きの資金を使ったときには,自分たちの行動が必ず制約される。したがって,本当に実現したいと思うことができない。Sulabh Internationalの主たる収入は,トイレの使用料金である。インダス文明衰退以来,野外排泄があたりまえのインドにおいて,誰がトイレ使用料を払ってまで綺麗なトイレを使うかという批判があったそうである。しかし最初の有料トイレを作って営業を開始した初日に,たくさんの女性が,それもどうみても富裕層ではない女性たちが,1ルピーを支払ってトイレを使うために並んでいたのを見て,Dr. Pathak自身たいそう驚いたそうである。これに関連して,Sulabh Internationalで開発した技術を海外に輸出して資金源にできるのではないかと質問したところ,Dr. Pathakは「われわれの技術は公共財である」ときっぱりと言い切った。「Professorが大学で教えていることも貧しい人たちの役に立つはずだ。その一つ一つ特許が付いていて,教えるために多額のライセンス料を学生から徴収しなければならないとしたらどうしますか?私は貧しい人たちを解放するための技術で金儲けをするつもりはありません。Sulabhの技術は,スカベンジャーの尊厳を回復するために開発されたもので,公共財以外の何ものでもありません」
ヒット曲「トイレの神様」からの受け売りだということだが,「日本ではトイレや環境を綺麗しておくことは,心を綺麗に保つことに繋がるんだけど,インドには同じような考え方はないのだろうか」という質問もあった。インドの野外排泄,ゴミのポイ捨ての実情を見てきた学生たちにとっては,自然に湧きだしてくる疑問であろう。Dr. Pathakは,インドにもそのような考え方が存在し,神話の中にも書かれているという。問題は,野外排泄やゴミをポイ捨てするということが環境を悪化させるという事実と結びついていないことである。たとえば,唾を吐くという行為も体の不浄なものを外に出して,体と心を清めるという宗教上の浄不浄感が先行して,それが外国人に不快感を与えるとか環境によくないという考えには結びつかないのだという。排泄も同じことであるが,人口の少ない時代にははきだしたものを自然が十分に吸収できたが,いまや10億を越えた人口が毎日排泄するものを環境が浄化できるとは思わない。「Sulabhの技術は,人々に気づかせ(awareness),態度(attitude)を変えることにも貢献しなければならないのだ」とDr. Pathakは語った。
時刻は午後1時を少し回っていた。「Dr. Pathak,われわれは,あなたの時間を使いすぎてしまったようです。そろそろおいとましたいと思います。最後に,おそらくは近い将来にビジネスマンとして国際社会に出て行く学生たちにメッセージをお願いできないでしょうか」。Dr. Pathakから次のような言葉をいただいた。「自分の信じることを,自分を信じてやってみてください。他人がどう思うか,何を言うかなんてことは二の次して自分の信じることをやってください。それが若者の特権であります。みなさんの社会(日本)は,そのような機会の平等が保証された社会だと思います。効率性は絶対に追求しなければなりません。でも効率性だけではいかんともしがたいこともあることも覚えておいてください」もちろんもっともっと長いメセージであったのだが,インド英語に多少は慣れてきた小生であるが,Dr. Pathakの英語は典型的なインド英語であり,小生にはそれを完璧に消化するには能力が足りなかった。次に機会があれば,自分自信をブラッシュアップする努力を怠らないのはもちろんであるが,できれば録音を許していただこうと思う。
最後に,Dr. Pathakと記念写真を撮っていただき,Sulabh Internationalを後にした。Gaurav氏は,来年のスケジュールが決まり次第教えてくれ,何でも協力する,今度はおまえの家族全員を連れてくるとよいと言ってくれた。
昼食は,タンドーリ・チキン発祥の店と言われる「Moti Mahal」でGoni Travel御用達の1000円ランチ(高い!!)。運転手は,昼食後に再びここに戻ってくるものと思っていたらしく,昼食後はホテルに戻るよう頼むととてもHappyそうな顔になった。小生がいたころは,車がなければとても来れないロケーションだし,どちらかというとローカルな食堂が好みだったので,ここのMoti Mahalは初めてである。レストランに入ると日本人だらけ。Delhiにいる日本人旅行者を総動員してしまったような賑わいで,東京のインド料理屋に来てしまったみたいで興醒めだ。確かにTandoori Chickenはなかなかの味であったが,他のものはそれほどでもないし,とにかく混雑し過ぎていて店員が十分に対応できていないのが残念であった。V3Sにここの支店と思われる「New Moti Mahal」という店があるが,そこの店の方が,雰囲気もゴージャスだし,料理の味とボリュームも勝っている。同じ金額を払うなら断然New Moti Mahalがよい。(2008年12月27日のTaj多事参照)
ホテルへ戻って明日の予定を確認して本日は解散。明日は観光で,電車でHaridwarへ行く。学生達は6時にホテルを出発していつものバスでNew Delhi駅へ向かう。朝食を5:30に食べられるようにお願いした。
小生と次男は,Karol Baghの駅まで歩いてメトロでSmile Innへ帰る。Rajiv Chowkで途中下車して,Jan pathのGovernment Cottage Emporiumへ行ってお土産を調達した。ここは,インド人客のほうが多く,店員が寄って来て押し売りすることが絶対にないので,ゆっくりと買物ができる。とにかく,このところのDelhiはえらく蒸し暑い。冷房の効いた店内に入るとほっとする。マクドナルドで冷たいペプシを飲んでから帰途についた。
Delhiの気温
最高気温 32℃
最低気温 26℃
平均気温 30℃
トイレ技術で不可触民を解放する
11/08/26

Sulabh Internationalのロゴにもなっているマニュアル・スカベンジャーの像。マニュアル・スカベンジャーは不可触民の中でも最も触れたくない人たちとされ,人の糞尿を乾式掘り込み便所から手で汲み取り,頭上の一斗缶のような容器に回収して処分場まで運ぶのが彼女たちの生業です。









朝の朝礼。
①歌に合わせてお祈りをするスカベンジャーの女性たち(向かって左側)。その右側にSulabh Public Schoolの生徒たち。後方にSulabh Internationalのスタッフが並んでいます。
②壇上に招待された私たちも合掌します。向かって一番右がDr. Pathak。
③,④Ms. Anitaが一人一人の名前を読み上げ,Dr. Pathakに花輪をかけていただき,アシスタントの女性にストールを肩にかけていただきました。予想外の丁重な歓迎に驚きを隠せません。
⑤朝礼後にDr. Pathak,スカベンジャーの人たちと記念写真を撮りました。
人糞で作った身体測定器。人体測定器と言われてもどのように使うのか見当がつかないのですが,メキシコの芸術家がSulabh Internationalの全面的な協力のもとにDelhiとJaipurで人糞を収集し,3年間をかけて乾燥させて21体を制作したそうです。向かって左は,われわれにトイレ博物館を案内してくれたガイドさん。ユーモアたっぷりにトイレの歴史と意義を説明していただきました。
Sulabh ShauchaiyaといわれるSulabh式水洗トイレ。ピンクの建家の中に便器があります。便器から出たパイプは二股に分かれてそれぞれが便槽に通じています。このモデルは,5人家族の2年もので,2年間で一つの便槽がいっぱいになります。いっぱいになった便槽は,次の2年間でガスと水分が抜けて,その残渣が堆肥になります。このトイレを使えばスカベンジャーが糞尿を汲み取る必要がありません。
Sulabh Shauchaiyaでは,有機物がバクテリアによって分解されることによって発生するバイオガスと,糞尿に含まれる水分と水洗の水を再利用していません。Sulabhのトイレ複合施設では,すべてが無駄なく再利用されます。バイオガスは,調理,電灯,暖房,発電に使われ,水はフィルタリングして植物に撒布されます。上の写真は,厨房でバイオガスを調理に使っているところで,下は水をフィルタリングする設備です。