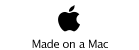Taj多事
2011
今日から25日まではRajasthan州に滞在してHumana People to People India(HPPI)のプロジェクトサイトを訪問する。
朝6:00にBharat Palaceを出発するので,4:30に起床し朝食を済ませて,セナさんの車で5:30にSmile Innを出発。学生達には昨晩,5:30朝食,6:00出発とフロントから電話で告げてもらった。やっぱり6:00になっても同じ部屋の2人がいない。他の学生に聞いても,「知らない」と言うだけで,誰かが迎えに行くわけでもない。結局,セナさんからフロントに頼んでもらって部屋に電話をするも応答なし,ボーイさんに部屋まで行ってもらってやっと出てくる始末。こういうことがあると「このゼミじゃ仕方ない」という声が聞こえてくる。確かに,ゼミを無断で休んだり,遅刻してくることに対して,小生はいちいち小言を言うわけではない。これを自由な雰囲気だと思うならとんでもない勘違いだ。合宿で『学問のすゝめ』を読んだ意味をもう一度考えてほしい。「俺は合宿いってないから知らな〜い」という声が聞こえてきそうであるが・・・
さて,これからの旅はセナさんが同行することができないので,小生がツアーコンダクターの役割も果たさなければならない。行き先は運転手も行ったことのない所なので,各所各所で相手先に電話をし,運転手に道を確認してもらわなければならない。さらにセナさんへの各所各所での報告も頼まれている。
我々を乗せた2台のミニバスの最初の目的地は,Rajasthan州のDausaで展開されているHPPIのバイオガス プロジェクトである。バスは,Delhiから国道8号線(NH8)で南西に向かいHaryana州のDharuheraへ向かう。Dharuheraに到着するまでにすでに2時間を要しており,道端のChai屋で最初の休憩をとる。こういうところで出されたモノを口にするのに抵抗のある学生も多いようだが,大方の学生がChaiを飲んだようだ。1杯10Rs.で,しめて160ルピー。
バスはさらに南下してRajasthan州のAlwarを目指す。AlwarのLifeline HospitalでHPPIの現地スタッフであるMr. Natthu Singhが,われわれに道を指示するために待ち受けている。Dharuheraを出発して1時間ほどのところでMr. Singhに電話をかけ現在位置を知らせ,Lifeline Hospitalまでの道を運転手に告げてもらう。さらに1時間ほど走ってLifeline Hospitalに到着。Mr.Shinghにもう一度電話して到着したことを告げると,ほどなく彼が現れ,目的地Dausaまでの道のりを運転手に説明する。
時刻はすでに10時を回っており,さらに2時間ぐらいかかりそうだから,目的地に着く前にどこかでランチをとった方がよいと運転手が言う。そのことを伝えるべくDausaのプロジェクト リーダーであるMr. Bharat Dayalに電話をするがつながらない。先方でも到着が遅いのを心配していたようで,先方から電話がかかってきて,運転手と話してもらう。先方もランチを先にとるように勧めているとのことだ。目指すDausaはRajasthanの州都JaipurとUP州でTaj MahalのあるAgraを結ぶ国道11号(NH11)沿いにあるそうで,NH11に出れば旅行者が多くたちよるレストランがあるから,そこでランチ休憩をとることにした。立ち寄ったレストランは,観光地によくある土産物屋といっしょになったもので,インド料理の味も外国人向けにスパイスが超控えめでとても物足りない。学生達の中には,すでにインド料理に食傷気味のものもいるようで,サンドイッチなどを食しているものもいる。
N11を西方にさたに走ってDausaのProject Green Action Dausaに着いたのは,1:00過ぎであった。プロジェクト リーダーのMr. Bharat Dayalのオフィスに通され,プロジェクトの概要を聞く。
バイオガス プラントとは,家畜として飼育している牛の糞と同量の水を発酵槽と呼ばれる貯蓄槽にためて,牛糞に含まれる有機物が無酸素状態でバクテリアによって分解される際に発生するメタンと二酸化炭素を含む可燃性ガスを調理や電灯の燃料として再利用し,残った牛糞の残渣を液肥や堆肥として農業活動の肥料として再利用する施設である。もし牛糞をバイオガス化しない場合には,女性が牛糞を回収し手でDung Cakeと呼ばれる牛糞燃料にして伝統的なChulaと呼ばれるストーブに焼べられる。不足する燃料は,女性と子供たちが周辺の森林から木の枝を拾い集めてChulaに焼べる。したがって,バイオガスを使うことができれば,女性は燃料を収集するために費やされていた多大な時間を別の目的に使うことができる。燃料木を拾うために学校に行くことのできなかった子供たちも学校に戻ることができる。さらに屋内において伝統的なChulaで燃料を燃やすときに発生する煙による屋内公害(In-house Air Pollution: IAP)も回避することができる。また,肥料の購入に費やしていた支出を節約することができる。
このように牛糞によるバイオガス技術は,インドの農家計においてメリットの多い技術であるが,もちろんその設置にはコストがかかる。HPPIのバイオガス プラントの場合,1日に25kgの牛糞が必要なプラントの設置コストが26 000Rs.で,これは農村家計にとってとても払える金額ではない。HPPIは主にフィンランド外務省より資金提供を受けてDausaの農家計にバイオガス プラントを設置している。これまでに22のバイオガス プラントがモデルケースとして設置され,稼働している。HPPIは同時に村に自助グループや農民クラブ(Self Help Group/Farmers Club)を形成し,バイオガスを使うことメリットを気づかせ,設置の仕方の説明や使うときのトレーニングを施している。3年後には農民達の手によって200のバイオガス プラントを設置することを目標にしている。
Mr. Bharat Dayalから一通りの説明を聞いた後,実際のプラントを見学するために村に入り,2軒の農家を訪問した。バイオガス プラントには,floatingタイプのもとfixed domeといわれる2つのタイプがある。それぞれのバイオガス プラントを使っている農家を1軒づつ訪問。Floatingタイプの発酵槽はインドで開発されたそうだ。Fixed domeに比べて高コストであるがガス漏れの危険が少ないそうである。一方,Fixed domeは中国で開発されたもので,鉄を使わない分,floatingタイプよりもコストが安くすむそうだ。いずれのタイプでも,最初に発酵槽を充填させてから,牛糞の有識質が分解してバイオガスとして使えるようになるまでに50日かかる。その後は,毎日一定量の牛糞を投入口から補充し続ければ安定的にガスを使うことができる。問題は,結婚式などで長期にわたって家を空けるときである。その場合に,自助グループや農民クラブが助けになる。たとえ自分の家にまだバイオガス プラントが設置されていなくても,学習によって使い方を周知しているので,留守の間の代役を果たせるのだ。訪問した2軒の農家はいずれも大家族で,「ナマステ」しか通じなかったが,家族全員が暖かく迎えてくれた。感謝。
Dausaの次のわれわれの訪問先はVirat Nagarのバイオ燃料 プロジェクトである。DausaからHPPIの人が1名同行してくれるそうだが,DelhiのHPPIオフィスからはDausaとVirant Nagarはすぐ近くと聞いていたのに,彼に寄ると80kmほどあるらしい。今日の宿泊先であるJaipurまでは,ここDausaからは50kmほどである。Virant NagarからJaipurまでは60kmほどあるから,これからVirant Nagarに寄るとすれば合計で140kmほどを走らなければならない。こんなに走るとは運転手には寝耳に水で,HPPIの付添人と揉めている。運転手はあわててセナさんに電話したが,セナさんからの返答は「お客さんの望むようにしてください」ということで渋々出発。
出発したはいいのだが,途中から道路は穴だらけで,バスはそれを避けながらクネクネと蛇行してして進むのでたまったものではない。誰も酔っぱらわなかったのが不思議なぐらいだ。途中,Sarisuka Tiger Reservation(トラ保護区)も通る,こんな所で車に酔ったあげくにバスを降りてトラに喰われてしまっては洒落にもならない。Dausaから北上して3時間かかってようやくVirant Nagarに到着したのは6時過ぎ。Virant Nagarのスタッフは3時頃の到着を予定してようだ。「どうしたんだ」と言われたが,このプランを組んでくれたのはDelhiのHPPIのスタッフなので,答えようがない。Delhiスタッフにとっては,インド流「No problem」ということだったのだろう。
バイオ燃料の原料作物であるJatropha(日本名ナンヨウ アブラギリ)を生産する村を訪問するはずであったが,すでに辺りは真っ暗で無理。Jatrophaからバイオ燃料を生産する試験プラントだけを見ていけということになった。実は小生は,ここへ来るのは2度目で,前回も全く同じ試験プラントをたっぷりと見学しているので・・・という感じ。でも学生たちにとっては初めての経験なので,ありがたく提案を受け入れる。ところが,その途端に停電・・・This is India.
停電が解消するまでの間,ここで展開されているMicrofinanceのプロジェクトの話を聞いたりなどしながら過ごし,30分もたったころにやっと電気が灯る。現地スタッフが実験プラントを稼働する。Jatorphaの種から油を絞り出し,それを蒸留機に投入するとディーゼル油とほぼ同質の油が得られる。ブラジルやタイで使われているバイオ燃料とちがって,石油燃料と混ぜることなく,このまま機械やバイクのエンジンを動かす燃料として使えるそうである。
Virat Nagarを早々に後にして,Virant Nagarから西方に向かってNH8に出て南下して,Jaipurに着いたのは7時半頃。当初の計画では,ホテルのすぐ近くのNiosで夕食をとってからホテルに戻ることにしていたが,まずホテルにチェックインして,シャワーなどを浴びてからNiosに出かけることにした。The Wall StreetではGoni TravelのJaipur agentが出迎えてくれ,16人分のチェックイン作業を代行してくれた。このホテルはとても綺麗で,おそらく4つ星クラスだろう。
8:00に再集合して歩いてNiosへ向かう。ここはJaipurを観光で訪ねるインド人に一番人気のインド料理レストランだそうだ。いくつかのテーブルに分かれたが,小生のテーブルは小生がメニューを選ぶ。Seek Kabab(マトンのミンチを竹輪状にして焼いたもの),Palak Panner(チーズ入りほうれん草カレー),Jeera Aloo(ジャガイモのインド煮ころがし),そして嫌いな人がいなそうなButter Chicken。疲れた体にビールが染みわたる。さすがにどの料理もおいしく,特にSeek Kabaは絶品!
朝食が7:00から食べられて,8:30出発することを確認して解散。写真をMac Airに取り込んで,携帯とカメラの充電をして,就寝。
Jaipurの気温
最高気温 34℃
最低気温 26℃
平均気温 30℃
牛糞バイオガスによる農家計の生活改善
11/08/23

バイオガスの原料は,農家で飼育されている牛の糞です。これまでは,女性達が牛糞を手で丸めて牛糞燃料(Dung Cake)を作っていました。バイオガス プラントのある農家では,女性はこれらの燃料収集作業から解放されます。

Floatingタイプのバイオガス プラント。このタイプの発酵槽はインドで開発されたそうです。Fixed domeに比べて高コストですがガス漏れの危険は少ないそうです。左の投入槽に毎日決められた量の牛糞と同量の水を入れます。Slurry(泥)化した牛糞は,真ん中下の発酵槽(Digester)でバクテリアによって分解され,上のガス ホルダー(Holder)に溜まります。ガス ホルダーの上部からパイプが出て,これが家屋まで引かれています。牛糞残渣は右側の槽に移されます。この農家では,slurry状の残渣を堆肥にしてから,畑の肥料として使っています。

ガス ホルダーの上部から出たパイプは,このガスコンロにつながっている。実際には火が出ているのだが,この写真では見えない。

Floatingタイプのバイオガス プラントを見せてくださった家族のみなさんです。みな笑顔で迎えてくれました。

Fixed domeタイプのバイオガス プラント。奥が投入口で,真ん中が発酵槽,手前が液肥槽。発酵槽の頂上から出たガス パイプが家屋につながっているのは上のものと同じ構造。このタイプの発酵槽は中国で開発され,floatingタイプのものに比べて低コストで作れるそうです。

この農家では電灯にもバイオガスを使っています。けれど,訪問したときには火が灯りませんでした。こういう事態にどう対処するかもHPPIの大事な仕事のようです。

Fixed domeを見学させていただいた家族の一部です。この家も3世代が暮らす大所帯です。