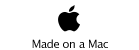Taj 多事
2010
31日と1日は,クシナガルで教育支援を行っている特定非営利活動法人「インド マイトリの会」を訪問した。クシナガルは仏陀が入滅した場所で,11月に日本の坊さんたちとの仏跡ツアーでも訪れた。そのとき,大涅槃寺に朝のお参りに来ていたマイトリの会の角田さんとお会いしたのが,今回の訪問のきっかけである。
デリーからクシナガルへは,鉄道でおよそ12時間かけてゴーラプールへ出て,そこからさらに車で1時間ちょっとの旅である。30日の夜8時25分出発予定の夜行でゴーラプールへ向かい,1日の午後4時35分の夜行で2日の朝デリーに戻るという少々強行な旅である。
今回は,家庭訪問の時の通訳をセナさんが買って出てくれた。30日の土曜は,7時にセナさんとともに家を出発して,メトロのブルーラインとイエローラインを乗り継いでニューデリー駅へ向かった。12番ホームから出発の予定であるが,時間になっても電車は現れず,何の放送もない。1時間ほどが過ぎた頃に「ゴーラプール行きの電車が12番線に入線します」とまるで定刻かのようなアナウンス。結局1時間5分遅れの9時30分にニューデリー駅を出発した。インドでは,この程度の遅れは時間通りと言う。
セナさんのお腹の調子がいま一つということで,ミナクシさんがお弁当を持たせてくれたそうだ。もちろんインドのお弁当はカレー。ジャガイモのカレーとパランタ,そしてヨーグルト。小生もご相伴に与る。とっても美味しい。インドの野菜のカレーは,ほとんど汁気がないので,お弁当にはとってもよい。これだけでは,足りなかろうと,列車販売の野菜ターリーも買ったのが,冷たくて最悪。汁気のないものは冷めてもどうということはないが,本来暖かいはずの汁気がほとんどのカレーが冷たいのはどうにもいただけない。
11時前には,それぞれのベッドに入る。ゴーラプールに着いたのは3時間遅れの31日の昼12時50分。タクシーというか,ただの車でタクシー的営業をしている運転手を捕まえてクシナガルまで700ルピーで交渉成立。あらかじめマイトリの会に値段を聞いておいたので,交渉もスムーズ。
仏跡ツアーのときと同じロータス・ホテルにチェックインして,すぐにマイトリ事務所に向かう。出迎えてくれたのは,ブラジェーシュさんというインド人男性スタッフで,日本人がいないときには彼が一切を任されているという。ちょうど昼食の時間だったようで,角田さんがちょっと遅れて迎えてくれた。30分ほど挨拶代わりの話をして,角田さん,ブラジェーシュさん,そして大学を1年間休学してインドでボランティアをしている東京外語大学の湯浅さんと歩いて10分ほどの村に向かう。
今回の小生の目的は,NSS(National Sample Survey)と似たような質問をすることにより,どのような家計がNSSのどの階層に分類されるているのかを目で見て確かめたいということである。クシナガルは,仏陀の涅槃像が横たわる大涅槃寺があるので観光客,お務めの仏教徒も多く,それなりにお金を落としていくので,極貧の村ではない。それでも訪問した村は,家こそ,屋根のある煉瓦造りのものであるが,大変貧しい家計の集まる村であることに間違いない。
村に入ると子供たちが集まってくる。おそらく20世帯以下の小さな集落であるが,見渡す限り子供だらけである。きっと村の平均年齢は15歳程度ではないだろうか,20歳には至らないと思う。たとえば,親が32歳と30歳で,12歳,10歳,9歳,7歳,5歳の子供がいれば,平均は15歳だ。親が40歳でも平均は17歳そこそこ。そんな家計が多く見えるのだ。
この日は3世帯で,インタビューをさせていただいた。
-
•家計1ー世帯主40歳(男性),職業は日雇い,ここで仕事があるのは年に半分ぐらいで,半年はデリーに出稼ぎに出る。月収は400ルピーから500ルピー(800円から1000円)。子供は6人。うち4人は学校に通い,2人は就学年齢前。親は,学校に通った経験がない。
-
•家計2ー世帯主はサイクルリキシャワーラー。仕事中で妻(30歳)がインタビューに応える。1日100ルピー(200円)の稼ぎがあればよいほうで,やはり半年はデリーに出稼ぎに出る。子供は5人で,5人とも学校に通っている。
-
•家計3ー自営業(雑貨屋)。世帯主は仕事中で,自称32歳の妻と24歳の長女がインタビューに応える。長女の年齢が正しいとすれば,妻が8歳のときに長女を生んだことになる・・・この家計は裕福で自称月3000ルピーの収入があると言う。学校のそばに構えている店舗の様子からすると,倍以上の収入があっても不思議ではない。子供は9人で,うち5人が学校に通う。4人は,すでに働いている。
どの家計も,電気は使えない,トイレはない,水は共同使用,ゴミは家の裏に捨てる。家計3は自転車を1台持っていたが,その他の家計は,ベッド以外に家具もなく,もちろん電気が必要な冷蔵庫も洗濯機もTVもない。携帯電話も持っていない。どの家計も収入のほとんどを食費に費やし,残りは貯めておく。なぜならば,毎日決まって収入があるわけではないからだ。どの家計も政府のPDS(Public Distribution System)を使って食糧や燃料などの必需財を安く手に入れることができるRation Cardを保有している。セナさんは,Ration Cardの存在すら知らない。Poorに対する一般人の認識は,そんなものなのである。
この村には電気は来ている。つまり政府が村を電化するということと,住民が普段の生活で使うことができるというのは,別のことなのである。引かれている電気は,農業のため(灌漑用の水をポンプで組み上げるための動力に変換する)で,家計には電線が届いていない。電気の代わりに灯りは灯油を燃やして得る。右の2番目の写真は,家計1で実際に使っている灯りである。ジュースか何かの空き瓶に灯油を浸した布を詰めて,その先を穴を開けた瓶の蓋から出し,そこにマッチで火をつける。これを2本使う。決して停電のときのバックアップではない。これが日常である。
火が直接出ているから,火傷や何かに燃え移る危険は常にあるし,煙もひどい,さらに何とも不安定である。調理には,牛を飼っていない家では木の枝を使う。チュラと呼ばれる調理台は,外(家にドアがないうえに,境があいまいなので一概に外とも言えないのであるが)に置かれているが,枝を燃やしたときの煙は,毎日家の中でたき火をしているようなものである。灯油を太陽電池ランプに置き換えるというLaBL(Lighting a Billion Lives)キャンペーンにそれなりの理由があることがよくわかる。
収入の額については,「月どのくらい?」と質問したのだが,家計3は明らかに過小に応えたと思うのだが,あとの2家計については,正直言って「1日このくらい」しか自分たちも把握していない。自分たちのことを正確に知らないのは所得だけではない。姓,年齢もわからない人たちも少なからずいる。姓については,それを明かすことによって自分たちが属する階級がわかってしまうということがあるから,わざと言わないのかも知れないが,本当に知らないということも否定できない。インタビューした3家計で姓を応えた家計は一つもない。年齢にいたっては,本当に怪しい。家計3の妻はいうまでもなく,こども達の年齢も相当に怪しい。どうみても就学年齢にいたっているとは思えない子供が,学校に通っている。親は,自信をもって6歳だと言うのだが・・・
過去に比べれば,決して経済的な条件がよくなったわけではないが, こういう家計でも 子供たちに学校に行かせようとする気持ちは増えてきているそうだ。そのために,食費に回さない収入は貯蓄をしようとするし,また女の子のいる家計では将来嫁がせるときの持参金も貯蓄の大きなインセンティブの一つである。
夜は,角田さん,ブラジェーシュさん,湯浅を小生達が宿泊するホテルで夕食にご招待。TERIで調達した子供向けの本4冊2セットを角田さんに手渡す。マイトリの事務所でも図書室を開設したところだそうで,ちょうどよかった。今日訪問した家計に何かお礼ができるわけでもない。お金を手渡すことは簡単であるが,それを目当てに我が家もインタビューしてくれと言われたり,マイトリの会に不公平だと文句が突きつけられる可能性もある。通常もう少し大きな調査をするときには,現地のNGOを雇い(たとえばマイトリの会),そのNGOに調査に必要な経費プラスαを渡して,その使い方についてはNGOに任せる。子供たちが手渡した本を眺めてくれれば,多少の恩返しになるだろう。
翌日(2月1日)は,学校を訪問した。メンバーはきのうと同じ。ホテルからマイトリの会の事務所に向かう途中,赤いセーターを身に付けた多くの子供たちに出会う。このセーターは,マイトリの会が配布したもので,累計8000枚に及ぶそうだ。
学校側は小生達が来るということで特別に出迎えてくれた。小生達が迷わないように,学校に向けて白線の矢印が引かれている。校門を入ると,子供たちが整列し,校長先生をはじめすべての先生方に出迎えられた。まったく恐縮でございます。授業の様子を少し見せていただければと思っただけなので,またっく予想していなかった事態にえらくとまどう・・・子供たちが整列する前に並べられたテーブルの中央の席に招かれて,子供たち全員のお祈り,国家,そして上級生二人による招待の歌を聞かせていただいた。
歓迎の式が終わると,子供たちは学年ごとに教室に入り授業が始まった。訪問した学校は半官半民で教科書は政府から支給されているが,ノートとペンはマイトリの会が配布したものだそうだ。一番下の学年の人口密度には驚かされる。3人掛けの机に6人が座っている。これでも半分程度の出席ということで,全員来たらどういうことになっちゃうの??日本の私立大学の場合も同じようなもんだけど。でも全員出席なんてことがないから,問題が生じたことがないから情けない・・・
インドの農村部における初等教育の大問題は,圧倒的な教員不足だそうだ。政府は教育が大事だということで,建物はやたらに建てるそうだ。この狭い地域にもなんと80もの学校があるそうだ。しかし,実際に児童が通い授業が行われている学校はほんの一握りだということだ。電力の場合でも電線が引かれていることで村が電化されたと政府は言うだろう。教育でも学校の数でその程度を誇示するかもしれない。しかし,実体はおよそかけ離れている。政府海外援助(ODA)も金だけ出して実際に有効に使われているか知れたものではないとよく批判される。連邦制ゆえであろうか,同じことが国内の資金配分でも起こっている。
校長先生の月給が15000ルピーから20000ルピー(3万円から4万円)。持家で農村部における生活なら十分な額であると思う。ただ,一般教員の月給は1000ルピーから2000ルピー(2000円から4000円)だそうで,これはあまりに低すぎる。建物の建設費の一部を人件費に充当すべきだろう。教員免許を取得した人たちの問題もある。多くは都市部の大学を卒業した若者たちだ。彼らが農村部で働くことを拒否している。働けども働けども自転車操業の毎日の生活を送らなければならい膨大な層を前にして,この若者たちは袖の下を払って働かないことを選択しているのだ。いったい教員を志願した理由はなんだったのだろう?教育への情熱ではなく,公務員として都市部で安穏な生活を送ることなのだろうな。もはや先進国病である。
昨年訪問したラジャスターンでもそうであったが,農村部の一つの大きな特徴は都市から隔絶されていることだ。ここクシナガルにしてもゴーラプールから交通手段は車しかなく,車を持たない農村部の人たちに都市部に出る機会はほとんどないという意味で物理的に隔絶されている。さらに電気がないことで,ソフト的な情報からも隔絶されている。訪問した家計では新聞すら読んでいる気配はない。それを考えたとき教師の果たす役割は非常に大きいと思う。少なくとも,世の中で起きていることを子供たちに伝えることによって,ソフト的な情報ギャップを少なからず埋めることが出来るし,子供から親へと情報は伝播する。そして,都市部で高等教育を受け,雇用機会に適応できる人的資本の形成,そしてそれがもたらす農村部の社会経済的発展に果たす初等教育と教員の役割は測りきれぬほど大きいはずだ。若者が大半をしめるこの国で,若者がその役割を放棄していては,未来は暗澹たるものである。自立したマニュアル・スカベンジャー達を前にしたパティル大統領のスピーチでも,この国にはもっともっとSocial workerが必要だと訴えていた。御意!!
角田さん,ブラジェーシュさん,湯浅さん,そして日本で連絡にあたってくれた吉田さん,それと同行してくれたセナさん,みなさんどうもありがとうございました。もちろん,クシナガルのみなさんと子供たちにも感謝。
2/3のデリーの天気予報 最高気温22℃、最低気温8℃、晴れ
2/3のデリーの天気 最高気温23℃、最低気温9℃、平均気温16℃
2/3の東京の天気 最高気温6℃、最低気温1℃、平均気温4℃
クシナガル
10/02/03



村に入ると集まってきた子供たち。とにかく子供ばかりに見える村なんです。左から2番目の女の子,6歳で学校に行っているというのですが,そのようには見えません。自分の年齢がわからない子も,親すら子供の年がわからない場合があります。
空き瓶に灯油を浸した布を詰めて灯をとります。毎晩,これを2セットつかうそうです。直接火が出ていて危険です。煙も出ます。不安定で倒れそうです。村には農業用の電力は引かれていますが,家計では使えません。でも政府はこの村は電化されているというでしょう。
1年生の授業の風景。机は3人掛けです。5人が当たり前で,2列目には6人が座っています。これでも出席率は半分程度だそうです。いったい普段はどんななんでしょう。児童が着ている赤いセーターはマイトリの会が配布したものです。登校時には村中真っ赤でした。浦和レッズのサポーターがインドまで来たかと勘違いしてしまうほどです。