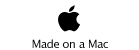Taj 多事
2010
今日の土曜は,ちょいと仕事をお休みして,スラブ国際トイレ博物館に行く。この博物館の存在は,旅行ガイド『Lonely Planet』で知っていたので,このような博物館はデリーにしかないし,機会があれば行こうかなぐらいに考えていた。しかし,ローズ・ジョージの『トイレの話をしよう』を読んでからは行かなくてはならない場所になった。
トイレ博物館は,デリー西部でインディラ・ガンジー国際空港の近くのMahavir EnclaveにあるSulabh Toilet Complexの中にある。このComplexは,Bindeshwar Pathak氏によって創設されたSulabh International Social Service OrganizationというNGOによって運営されている。Pathak氏は,マハトマ・ガンジーの「不可触民の解放」の精神を受け継いで実行するために,この非政府組織を立ち上げた。不可触民の中でも,マニュアル・スカベンジャー(ヒンディー語でサファイ・カラムチャリ)と呼ばれ,素手で糞便を処理する仕事を強いられている人々を解放するすることを中心に活動している。サファイ・カラムチャリは,その職業故に,他のものと食事の席を共にすること,同じ水を使うこと,その子供たちは学校においても他の子供たちと同席することすら許されていない。まさに触ってはいけない存在なのだ。
もちろん独立後のインドに,不可触民は法的には存在しない。ガンジーらの解放運動は1949年のインド憲法第17条に「不可触性の廃止(Abolition of Untouchability)として「「不可触性」を廃止する,いかなる形態においても不可触性が行われることを禁止する。「不可触性」故に強いられる不自由は,法の下に罰せられる」(訳は小生によるものなので原文も書いておこう。17. Abolition of Untouchability. “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an offence
punishable in accordance with law.),と具体化された。
しかし,小生が見るインドでは,上級階級,もちろんこんなものも法的には存在しない,だと自分自身のことを思っている人たちは,子供も含めて,この廃止された制度を都合よく利用している。つまり,憲法違反を平気で犯している。掃除をしてくれる不可触民がいるから,ゴミを路上にポイ捨てすることをなんとも思わない。小生が見た「膝から下の世界」である。『トイレの話』によれば,サファイ・カラムチャリを雇う自称上級階級の人たちは,この誰もが嫌がる仕事に対して,食べかけの残飯と1ヶ月5ルピー,10円の賃金しか払わない。素手で糞便を処理するわけだから,常にさまざまな感染症の危険に晒されている。たとえ,下痢に嘖まれ,病気になろうとも医者にかかるお金はない。最悪,死を待つだけである。
小生が使っている2004-05年のデータによれば,指定部族,指定カースト(不可触民),その他の後進階級に属する世帯はインド全体で70%,都市部で54%,農村部では74%にもいたる。10年間もの間,年率8%から10%の経済成長を達成した国家で,いまだたった30%の人口が70%の人口を支配する奴隷制度を保持している,少なくとも教育を受けた人々の多くがこのような状態を都合よく利用している,さらにその首都において平気で人々がトイレを使わずに糞尿をたれている,そんな国家が第2次世界大戦の後の世界に存在しただろうか?COP15においても,中国の暴挙に対してG77の多くの途上国が反発する中,インドは何も言わなかった。鳩山首相が訪印して核廃絶への協力をお願いしたときにも,アメリカと中国がそうするならという答えであった。I’m very disappointing!である。
そもそもカースト制度は,アーリア人がモヘンジョダロやハッラパに代表されるインダス文明を築いた人々やインド原住民を侵略したときに,ヒンズー教の元と言われるバラモン教を利用して,これら先住民族を支配するために制定された制度だと言われている。後にインドを支配したムガールなどのイスラム文明もそれを利用したし,1600年に東インド会社が進出してからの大英帝国はさらにその制度をひどいものしたと言われている。カースト制における不可触民あるいは指定カーストは,江戸時代の日本の士農工商制における「えた非人」と何ら変わらない。日本でも部落問題はいまだに存在するが,インドのように日常の生活に浸透しているわけではないだろう。1947年にインドは大英帝国からの分離独立を果たしたが,大英帝国の残した負の遺産をいまだ都合よく使い続けているというのは,いまだ大英帝国の支配下にあることと変わらないのではないだろうか。
その現状に立ち向っている人の一人が,Bindeshwar Pathak氏だ。便所の構造が悪いからサファイ・カラムチャリが必要になるというのが彼の着眼点だ。インドの伝統的な便所は,日本のものと同じようにしゃがんでふんばるタイプのもので,いわゆるドッポン便所である。サファイ・カラムチャリを雇う家計では,糞尿を一定期間溜めてバキュームカーに汲み取ってもらうのではなく,サファイ・カラムチャリが便器の下に入り込み毎日毎日掃除をするのである。サファイ・カラムチャリは,ブリキの板あるいは素手で掬い取った糞便を石油缶のようなブリキ缶あるいはカゴに溜めて,それを頭に乗せて近くの廃棄場所まで運ぶのだ。頭に糞便を溜めた缶を乗せて歩く女性のサファイ・カラムチャリの姿は,スラブのロゴとして使われている。
パタク(Pathak)が考案した便所は,2リットル以下の水で流せる傾きを持った便器を持ち,一つの便器には二つの便槽が備え付けられ,それらを一定の間隔(4,5人世帯であれば90日)で交互に使う。使わない90日の間に溜められた糞便は堆肥になる。このバイオ便所をスラブが貧困世帯に備え付けているのである。また,インドで7500箇所に設置されたSulabh Toilet Complexと呼ばれるスラブ公衆便所では,堆肥だけではなく,発生したメタンガスを発電,厨房,暖房用に使い,濾過した水も敷地内の灌漑用に使い,庭の芝や草木に与えられている。Complexで使うエネルギーは,全て糞便からリサイクルしたガスで賄われ,外部からは一切調達していない。
このような便所が使われることによってサファイ・カラムチャリの仕事はなくなるわけだが,同時に失業に状態に陥ってしまう。そこでスラブでは,サファイ・カラムチャリの職業訓練も同時に行っている。女性には,タイピスト,美容師,男性には電気・電子機器の修繕などの職業訓練が実施されている。
さらに,サファイ・カラムチャリに限らず,後進階級に属する人たちがそうでない人たちと同化できるように,後進階級の子供たちの教育のための学校も運営している。小生が訪れたデリーの学校では,その4割は非後進階級の子供たちで,すでに同化が実現している。
2008年7月には,国連のUNDESA(United Nations Development of Economic and Social Affairs)にスラブの活動で自立したサファイ・カラムチャリの女性達が招かれ,さらに彼女達はインドのパティル大統領からも王冠を授与された。
ここまで書いてきたことは,一部『トイレの話』による部分もあるが,ほとんどは今日,スラブを訪問して得た情報である。当初,いわゆる博物館を想像して出かけた小生であるが,目的地のそばに着いてもそのようなものは見当たらない。ただ,「スラブ トイレ団地(Sulabh Toilet Complex)」という看板があって,「博物館」という矢印があるが入り口はどこにも見つからない。とにかくトイレ団地の職員らしき人に「博物館はどこですか?」と聞いてみると,「こちらへどうぞ」と敷地の中に案内され,緑の芝の中庭を横切って,トイレの展示場のような場所の隣にある部屋に通された。これが博物館で,日本式に言えば20畳もないようなこじんまりとしたものである。もちろん見学者は小生一人だけである。
しばらくすると若い男性が現れて,「これからこの博物館の展示について説明をしますが,そもそもどのような目的でこの博物館を訪問されましたか?」と,ほかの博物館なら絶対に聞かれない質問がいきなり飛んできた。その寸前までおのぼりさんモードだった小生は,お仕事モードに豹変。「実は,『トイレの話』を読んで,この組織が貧困の削減と環境の保全を両立させるという意味で,環境と社会の持続可能性を達成する仕事をしていることを知り,興味を持って訪問しました」「お仕事は何ですか」「大学で研究をしています」「わかりました少々お待ちください」。
再び現れたときには両手に一杯の資料を携え,「研究の参考になるかもしれないのでお持ち帰りください」といきなりお土産をいただいた。「これからお話することは,差し上げた資料にも書いてありますが,大事なことだけをお話させてください」ということで,およそ30分にわたりトイレの歴史と現代についての講義を受けた。インダス文明を代表するモヘンジョダロの遺跡からは,すでに水洗式のトイレと下水設備が発掘されていて,糞便のリサイクルに関する証拠も見つかっているそうだ。しかし,洪水などによるインダス文明の崩壊とその後勃興したローマ帝国によってその伝統は断たれ,糞便に関する暗黒の時代が始まり現在に至っているというのが話の大筋だ。そして,ローマ帝国による悪業をモヘンジョダロの時代のものに回帰させようとする試みのいくつかが紹介され,その一つの試みがスラブの試みであることが説明された。
その後,豪華なソファのある応接室に通され,このトイレ団地の代表者の一人であるChandraさんに紹介していただいた。チャンドラさんに,ぜひ学校も見せていただきたいとお願いすると,「もちろんOKです。まず学校に行って,次に技術者にここで開発したトイレの説明を受けてください。その後でまたお話しましょう」。
博物館の説明をしてくれた男性に学校に連れていってもらい,校長から学校の説明を受けた。この学校には5歳から16歳の460名の子供たちが在籍し,そのうち60%がサファイ・カラムチャリの子供たちで,残り40%が非後進階級の子供達だそうだ。後進階級の子供たちを同化させるために授業は全て英語で行われ,バラモン(カーストの最上位で神事を司る階級)しかもはや学ばなくなっているサンスクリットも勉強させているそうだ。その他,大人たちも含めた職業訓練の教室がある。今日は土曜日で,学校を訪問した時間は午後2時を過ぎていたので,子供たちの授業の様子を見ることはできなかったけど,英語の文書をタイピングする職業訓練を受けている女性達のクラスを少しだけ見せていただいた。みな真剣そのものだった。
トイレ団地に戻り,女性の研究員からスラブ式トイレの技術的な説明と,バイオガスや水のリサイクルについての説明を実物を見ながら受ける。内容は上述した通りである。
その後再び応接室に戻りチャンドラさんとお話をさせていただいた。スラブの活動は,すべてスラブの建てた公衆トイレからの収入で成り立っているそうだ。たとえ有料のトイレであっても,子供は無料で使用できるし,普通の人たちにとっては綺麗な環境で用を足すための1ルピーは苦にもならないということだ。確かに街中にある公衆トイレは,入るのをためらうほどに汚い。そこまでは来たけれども,トイレを使わずにその隣で用を足している人をよく見かける。貧困世帯へのスラブ式トイレの供給は,すべて公衆トイレからの収入で無償で行っている。大事なことは,これまでの慣習を捨ててトイレを使わせることで,トイレを使わないことによる危険について気づいてもらうこと,チャンドラさんの言葉では「awareness」がプロジェクトを進める上で最も大事な要素だという。教育の重要さをここでも確認することができた。ぜひ日本の学生にもこうした活動を紹介したいし,機会があれば連れてきたい,そして研究の上でもっとお話を伺いたいことが出てくると思うので,これからも連絡をさせてくださいとお願いしてトイレ団地を後にした。
博物館見学という軽い気持ち出発したけど,2時間半に渡って非常に貴重な時間を過ごすことができた。2010年になってまだ2日目であるが,昨日の老紳士といい,貧困や雇用の問題についてもっとしっかりやれと,尻を叩かれたような2日間であった。TERIの若い連中には,分析モデルの中に雇用,所得分配,貧困を組み込まないと時代遅れになることを何度も繰り返し話してきた。もちろんTERIがそのような側面を無視しているわけではない,でも小生が今一緒に仕事をしているグループがモデルによって描く将来のエネルギーシステムについて,これらの側面が考慮されていないのは全くの片手落ちなのだ。今度2010年の国際産業連関学会で報告する論文の一つは,まさにこの側面に焦点をあてる。やっと口酸っぱく言ってきたことが実現しそうだ。
トイレ博物館のあるMahavir Enclaveまでは,メトロのブルーラインでDwarka Sector 10まで行き,そこから徒歩で45分である。小生が毎日使うYamuna BankからDwarkaまではブルーラインでデリーを東西に端から端まで旅することになる。乗車時間にして約1時間。でも料金は27ルピー,34円でしかない。Dwarkaは新興の住宅団地で,6階から7階建てのモダンなアパートが林立している。メトロの駅名についているSection番号は,団地の区画番号で,区画を分かつ道路にも番号がふられていて,一つ一つの道路も巾が広く,非常によく整備されている。学校も区画ごとにあるようで,いずれも大変綺麗な校舎であった。この住宅団地は,小生が暮らすシャカルプールやラクシュミナガルの様子とは全然違うし,コンノート・プレースなどの繁華街とも違うし,ジョルバーグやディフェンス・コロニーなどの旧植民地を彷彿とさせるような高級住宅街とも全然違う,新しいデリーの顔のようだ。
それでも貧困とは無縁というわけではないようで,暖を取るため調理のための薪を集める子供たちに何度も出くわした。住宅団地を抜けてMahavir Enclaveに入ると,一気に従来のデリーが顔を見せ,その一区画にスラブ トイレ団地がある。住宅団地とトイレ団地の中間点にあるガソリンスタンドでは,「Pollution Checking Center(公害検査所)」なんてデリーの中心ではみたことのないものまであって,バイクが排気ガスの成分を検査しているようだった。 たかだか45分の歩きであるが,いろいろなデリーの表情を見ることができて面白い。これが車の旅では味わえない,おもしろさだろう。
コンノートのラジブ・チョークに戻ったのは5時を過ぎていた。食事には早いし,どこかに行くには時間がなさすぎるし,えらく中途半端な時間である。昼飯を完全に食べ損なってしまったので,まずはAブロックのWengerでShami Kababを食べることにした。隣に並んでいたMushroom rollがえらく旨そうに見えたので,一個づつ買う。 まずは,Mushroom rollにかぶりつく。うまーい。ピリッと辛い,マッシュルーム入りクリームコロッケだ。やみつきになりそうだ。
こないだ買ったインディアン トラディショナルなベストがお気になっているので,他にいいものはないかしらとKadhi Indiaに入る。んー,2着買ってしまいました。
6時半になってしまったので夕食のレストランを探しに歩く。こうして食べ歩くことも,あと5,6回しか機会がないので,新しい店を開発するというよりは,おいしかったものをもう一度食べてもよいと思っている。Kadhi Indiaから外周を歩いていると,まだ入ったことがないけどカルティックからも評判がよいと聞いているVedaというレストランに出くわした。ただ,一人で入るにはあまりにも雰囲気がロマンチック過ぎるのでパス。United Coffee Houseでハイデラバード風チキンカレーをもう一度食べようと内周へ抜けて店の前まで来たが,すでに長蛇の列。観光シーズンなんですね・・・その先にあるEmbassyは,前回来たときも悪いイメージではなかったし,空いていたので,入ることにした。Vegetarian Seekh KababとChicken Masalaを注文したけど最低。まさか観光シーズン特製の外国人特別レシピじゃあるまいな。まるでスパイシーさがなく,Chicken Masalaときたらクリームシチューじゃないかと思うほどだ。もう,明日にでも旅行者が来そうにない食堂で口直しをしないと,どうにも我慢できません。
1/2のデリーの天気予報 最高気温22℃、最低気温5℃、晴れ
1/2のデリーの天気 最高気温15℃、最低気温8℃、平均気温12℃
1/2の東京の天気 最高気温10℃、最低気温1℃、平均気温6℃
トイレ博物館
10/01/02

トイレ博物館は,この敷地の中にあります。このComplexは,マニュアル・スカベンジャーという素手で糞便処理をすることを強いられている人々を解放するための,デリーの拠点です。

トイレ博物館は,デリー・メトロのDwarka Sector 10から徒歩で45分ほどのところにあります。Dwarkaは新興の住宅団地で,6階から7階建てのアパートが林立し,区画整理も行き届き新しいデリーを象徴しています。

だからといって貧困と無縁といわけではありません。写真のように,調理の燃料,そして暖を取るための燃料として薪を集めている子供たちに何人も出会いました。この子たちは,上の写真の学校には行けないと思います。

学校も区画ごとにあるようで,とても立派な校舎です。