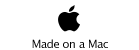Taj 多事
2008
今日も6時20分に起床。Dewaliのおかげで早く起きられない。今朝も静かだ。読書をして、8時に家を出る。いつものオジさんは、今日もいない。それでも客が少ないと見えて、何台かのRickshawが手持ち無沙汰に客を待っている。運転手が歩いて寄ってきて乗れ乗れと手招きする。Rs.80で譲らないのだが、まあいいか。道がガラガラといってもよいぐらい空いている。20分かからずにIHCに到着。
TERIのスタッフも8割は出て来ているのではないだろうか。Dewaliの休みの間に、Top downモデルとBottom upモデルの連携にかんするpaperを探しておいたので、さっそく慶應の図書館からダウンロードして、午前中はそれらを読む。
13時半に昼を食べにGulba’sへ。今日は、はじめてこの店のChineseに挑戦して、Chili garlic chowmein(辛いニンニク焼きそば、Rs.40)を注文。これも量が多い。味は、美味しいのだが、あとから辛さがじわじわとやってきて、頭の天辺から汗が流れ出る。オフィスに戻ってからもしばらくは汗が引かなかった。いっしょに三種類のソースが出された。となりのインド人も焼きそばを食べていて、赤いチューブに入ったソースをやたらかけているのでチリソースか何かかと思って、ちょとだけかけてみたらトマトケチャップではないか。変なナポリタンになっている。あとの二つは、辛いソースで、これを少々かけてしまったのも大汗の原因かな。
午後も、モデルのpaperの続きを書いて、5時20分にTERIを出る。最近は、東口から出てRickshawを探しながら西口の方へ歩くようにしている。今日も2台目の車とRs.90で交渉成立。「Shakarpur Jamuna Paar」に続けて「On Mother Dairy Road」というとすぐに場所を把握してくれるようだ。往きも初めての運転手には「Habitat Center on Lodhi Road」というと「Lodhi Road」と聞き返して来る。やはりRickshawワーラーにとっては道の名前が一番わかりやすいようだ。
15分ほど走ったところでガス・ステーションに入ってしまった。日本のタクシーじゃ客をのせてガソリンスタンドに入るなんて考えらないけれど、回りを見るとこの地では当たり前のようである。客を乗せないで車を走らせてガスを充填しに行くのは、たしかに無駄である。この地のほうが合理的だ。自分で車を運転しないので(この地では絶対に運転したくありません)、貴重な体験だ。Auto Rickshawには、CNG(Condensed Natural Gas)という環境に優しい燃料を使うよう規制されている。気体のガスをシューッと充填するのだ。Rs.20払ったように見えたのだけれど本当のところいくらなのだろう。
ガス・ステーションを出てすぐのところで、この運転手も立ち小便だ。何でガス・ステーションでやらないの!おまけにちょっと高いところにのって堂々と放尿している。風邪向きが変わったら、飛沫がこちらに飛ぶから隠れてやってくれ!この運転手は、手を洗わずに運転続行。
途中から見知らぬ道をどんどん走って行く。最近は、こういう事態にも慣れっこで、いつもと違う景色を楽しむ余裕がある。いつもと正反対の方向から、いつもの場所に到着。あきらかに遠回りで、道がすいていたにもかかわらず、45分かかった(ガス充填時間含む)。
家に戻ってすぐに、スーパーに買い物に出かける。いろいろ見ていて気がついたのだが、スナック菓子にもベジタリアン用、ノンベジタリアン用があるのだ。食堂でもノンベジタリアン用には、白地に赤の日の丸マークがついていて、ベジタリアン用には緑の日の丸がついている。そのマークがポテトチップスなどのスナックにもついている。コンソメ味なんてのは、ベジの人は食べないわけだ。
今晩も爆竹が続いている。
今日の仕事のまとめ。
午前中は、Top downモデルとBottom upモデルの連携に関する最近のペーパーの何本かを読む。いまやっている仕事は、まさにその範疇に入るので、他の人の仕事もしっかり押さえておかないといけない。この議論は、地球温暖化対策に関する経済モデルによる分析が盛んになって以来、すでに15年は議論されている問題なので、何か新しい進展はないのだろうかと期待していたが、正直言って、特にない。
Bottom upモデルのデータを使って、CGEの生産関数のパラメターを基準ケースでBottom upモデルと同じエネルギー効率になるようにcalibrationするなんていうのがもてはやされていたりする。熱力学の情報も考慮入れた生産関数などと言っているが、ちょっとというか、大分勘違いしているのではないだろうか。生産工程別にLeontief型の投入係数ベクトルをつくり、そのベクトル間に代替の弾力性を設定するというモデルもあったが、これなどはまともな方だ。Bundle approachというのもあるそうなので、明日はそれを見てみよう。
気候変動の問題についてInduced technical changeによる技術変化の内生化というモデルも注目を集めている。60年代にも同じ名前のついたモデルがあったが、Grilichesが痛烈なコメントを浴びせていたとを思い出した。JorgensonのところにいたRFFのPizerが展望論文を書いているの読んでみよう。こういうモデルで、CCSなど新しい技術の分析ができるのだろうか。優秀な頭脳をもっと別の方向で使っていただいたくのが生産的だと思うのであるが...読んでからにしよう。
午後は、TERIのエネルギーモデルのベースであるMARKALをIOベースに書き下すことを試みる。そうすることによって、今回考えているモデルが、エネルギーモデルのどの程度の内容を取り込むことができているのかがはっきりとするはずだ。現段階で明らかに異なるのは、生産能力が内生的に決まって、それに応じて投資がなされるという形で動学モデルになるのだが、各期の生産量が生産能力以下であるという制約を課していないことだ。理論モデルとしては可能である。しかし、今回はモデルが非線形最適化モデルにならざるを得ないので、選択変数をできるだけ少なくしたい。もちろん各期の生産量を選択変数にすることもできるのであるが、インドの産業連関表は130部門でこれを10期解いたとしても1300個の選択変数について最適化をしなければならない。現代の数値計算能力を持ってすれば許容範囲なのかもしれないが、そればかりはやってみないとわからない。また、詳細に技術を記述するという意味で、部門数は増やす可能性はあるが、減らす方向では考えたくない。
今回は、Technology Utilizationと呼んでいる変数を選択変数としたので、技術選択を行わない部門があればその分だけ選択変数の数を減らすことができる。モデルを解いてみないと、Under utilizationなのかOver utilizationなのかがわからない。それが計算の結果を分析するのに役に立つのは間違いないし、それを能力拡張投資や、時期の市場への供給量に結びつけるという形で、長期の技術選択の問題と短期の生産量調整の問題を同時に扱える可能性も出て来ると思う。
スナック菓子にもベジタリアン
08/10/30


Gulba’sのChili garlic chowmein(Rs.40)。辛さがあとを引きます。
Rickshawのガス・ステーションを見学できました。