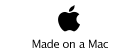Taj 多事
2008
5時半起床。7時半まで読書。7時45分に家を出て、いつものオジさんのRickshawでIHCまで行く。昼はGulba’sで食べようとしたのだけれども、明日のお祭りのためのお菓子屋だけの営業で、レストランは休業。しょうがないので、EatopiaのVegetarian Thali(Rs.120)を食べる。さすがに、このThaliもを飽きてきたので、何か単品だけの注文をしてみよう。というより味と値段を比較したら圧倒的に外の方がお得なので、なるべく外に行こう。
小生より少し奥の方に席がある年配の研究員は、いつも小生の後ろを通って出入りする。その人が、「Are you mathematician?」、「No」。確かに、デスクに積んである本の一番上は、Econometricsの本だし、ノートを見ても、コンピューターのディスプレイに映し出されている書きかけのpaperも見ても、数式が多いので、そのように思う人もいるかもしれない。3Fでデスクを間借りしていたときには、数式の一杯詰まった工学系の本を並べている人もいたのだけれど、必ずしもそういう人ばかりでもないらしい。今やっていることを少々説明したのだけれど、わかってくれただろうか?
4時ぐらいからTERIのみんさんは、「Happy Diwali」といって帰る人が目立ってきた。まさに、クリスマス、正月という感じだ。小生も5時15分ごろにオフィスを出た。
帰りも1台目のRickshawがRs.100でOKしてくれた。ただ、いつにない渋滞で45分ほどかかった。運転手も途中で小便が耐えきれなくなって道端で用をたす。車に戻ってくると、椅子の下から水の入ったペットボトルを取り出し、手を洗う。この辺の衛生感覚がよくわからない。自分の手は綺麗にするけど、公衆衛生はどうでもよい。ちなみに洗ったのは左手だけ、一物は左手だけで持つようです。
家に戻って、きのうと同じく、円高に乗じて家賃を降ろしにV3Sへ行く。超現代的ショッピングモールV3Sへ入る直前にも公衆トイレがあるのだが、これはひどい。便器の下は、穴を掘ってあるだけであふれんばかりである。この国も、最低限の公衆衛生、電車、バスなどの交通機関が確保できるだけでも、随分と暮らしやすくなり(外国人の感覚ではあるが)、感染症や公害に起因する疾病などの多くを防止できるのではないかと思うのだが。
車に関しては、かつては運転する人と乗る人は区別されていて、乗る人は決して運転しなかったわけであるが、いつの日からか中間層が、自分で運転して、自分も乗るという掟破りを犯したために、今のような渋滞、騒音、排ガスなどの問題を生じてしまったのだと語気を荒々しくする人もいる。さらには、洗濯機や掃除機まで買って、アウターカーストの職まで奪ったと主張する。映画『ガンジー』で、ガンジーの奥さんがアシュラムの便所掃除をハリジャンではなく自分がするのかと涙したシーンを思い出す。最初の掟破りは、ガンジーなのでは?
V3Sの敷地内で所によって、小さな虫が密集した蚊柱のようなものに遭遇する。 手で払いのけてもなんの効果もなく、目もあけてもいられない。体中の穴という穴は全部閉じておかないと大変という感じだが、尻の穴ぐらいしか閉じられない...
とにかく町は賑やかである。クラッカー、花火、楽団、人の声、車、バイクのクラクション、自転車のベル。これでも経済が不調のせいで、いつもの半分だとセナさんは言う。今、夜の10時半であるが、外は市街戦の様相だ。あしたが恐ろしい。
朝の読書の時間は、Jeffery D. SachsのCommon Wealth, Economics for a Crowded PlanetをCDの英語を聞きながら読んでいる。15年前にHarvardにいたときには、彼はInternational Financeの講義を担当しいたが、そのときも難しいことを随分とわかりやすく説明できる人だと感心した。その当時からボリビアやロシアのハイパーインフレーションを阻止するために奔走してHarvardにいることが少なかったので、 当時流行っていたWhere is Wally?にひっかけて Where is Jeff?などと冗談でいわれていた。その後アフリカ、インド、中国の途上国などの経済政策に携わるようになり、現場に密着した「臨床経済学」を提唱し、国連のMillennium Development Goalsをアナン事務総長のもとでまとめ、ベストセラーとなった『貧困の終焉』を著した。Sachsは、Columbia大学の地球研究所(The Earth Institute)の所長になるためにHarvard大学の職を辞した。彼にとっても悩みに悩んだ決断だったと回顧している。地球研究所での多岐にわたる仕事を啓蒙書として記したのがこの書である。これまでのSachsは、国際マクロ経済学における純粋理論的貢献だけでなく、計量経済学的に測定された方程式による新古典派とケインジアンを折衷したモデルを器用に使って様々な政策的課題に答えてきたという印象がある。最近の彼の仕事は、みずから臨床的というように、現場に自ら赴き、よく観察し、その現場現場で何が問題になっているかを、経済指標だけではなく地理的条件など様々な視点から聴診器を当てるかのごときに分析し、個々の患者に適した処方箋を書くというスタイルに変化している。
この著書の最後に、平和で持続的に発展する世界を築くという願いを実現するために、われわれができる八つの行動をあげている。その第一番目が気に入っている。この世代が挑戦すべきことについて学ぶこと。持続的発展という考え方の根底にある科学についての知識を身につけること。そのために、就学過程にあるものは、環境、経済発展論、気候変動、公衆衛生、その他関連する分野のクラスを履修すること。そうでないものは、科学的発展に関する情報の身近にいられる方法を見いだすこと。Nature, Science, New Scientist, Discover, Scientific Americanなどの週刊誌、月刊誌は、われわれの世代にとって必読の出版物だ。それらが語っていることのほとんどは理解できないかもしれないけど、現代の科学が挑戦すべきことは何か、新しく発見されたことは何なのかという情報を与えてくれる。科学的思考と科学の発展を常に意識するためにも質のよいWebサイト閲覧するのもよい。
Sachs自身が、この行動を最も忠実に実行している人にちがない。 学生には、環境、経済発展論、気候変動、公衆衛生にプラスして、Common Wealthを読むことを勧めたい。そして、経済学を学ぶ学生に、その周辺分野の知識を身につけると同時に、経済学の一分野としての経済発展論をぜひ勉強して欲しい。なぜならなば、既存の理論では、どうにもこうにも説明出来ない現実について、そして既存の経済学がなるべく避けようとしている不平等の問題について、多いに悩んでいるからだ。同じように聞こえるかもしれないが、経済成長論のテキストを読んでみれば、数学的にはソフィスティケイトされているかもしれないが、この方程式のこの前提をこういうふうに変えてやれば、たとえば蓄積する生産要素の限界生産力逓減しないようにしてやれば、人口が一定でも、外生的な技術進歩率を与えることをしなくたって、永久に成長し続ける素晴らしい世界を描けるじゃないか、だからもっと研究開発をしようよ、教育投資をしようよ、そんなモデルばかりである。そんな世界だれもみたことないにもかかわらず。
自分が生きている時代の課題、自分の次の世代の課題について学ぶためには、そもそも社会が様々な分野の発見、発明、知識、文化、制度の集体であるのだから、基本的なことについての全方位的な学習が絶対に必要である。大学に入るために、高校で数学と理科をやらないとか、国語と地歴をやらないとか、そんな近視眼的な行動を大人が許しているようでは日本の将来は暗澹たるもので、Sachsのいうチャレンジのため行動など実行できるはずもない。つまり国際社会から置いてきぼりを食うだけだ。
ディワーリー・イブでも外は市街戦
08/10/27


近所の商店街もものすごい人出です。
これでも例年の半分だとか。
人も多いけど虫も多い。電灯の回りがぼやけているのは虫のせいです。目も開けられません。虫も例年の半分ならいいんですけど...