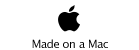Taj 多事
2008
5時起床。昨晩は、日記をつけずに早々に寝てしまったので、続きを書く。隣の部屋にもシャワーはないので、隣の住人が起きる前に洗濯を済ませてしまう。おーっと、気がついたら向かいの部屋にも新しい住人がいるではないか。コンファレンスでもあるのかな?外を観ると雲行きが怪しい。風も吹いている。インドでは一度も雨に遭遇していないので、どういう降り方をするのか想像ができない。とりあえずカッパをリュックに入れて、リュクをリュックカバーで覆って、傘をすぐ取り出せるところにしまって、出発だ。濡れることを考えたらサンダルがいいだろう。
外に出ると涼しい。やっと秋到来か?このぐらいの気温だと過ごしやすい。今日も陸橋通りを歩く。歩きながら考えたのだが、雨が降れば、この道に落ちている牛やら犬やらのウ○コは、流れ出すにちがいない。サンダルだと直にウ○コがつく危険性がある。でも靴だといつまでも臭うかもしれないなー。雨季が怖い。くだらないことを考えている間に到着。雨は降らなかった。
今日は、Rituが来ている。京都から戻って、熱を出して休んでいたとのこと。ということでまた遊牧民に戻る。しかし、今日は、3Fでいよいよ大移動が始まった。3Fの奥の方には、ガラスで囲まれたブースのような個室が三つある。そこは、各Divisionのマネージャー級が入る部屋のようだ。いつの間にか、そのうちの二つが空きになっていて、そこへフロアから二人が引っ越しする。その一人がRituだ。
この引っ越しもおもしろい。いっさい本人は、手伝わない。机の上から、引き出しの中まで、全部使用人がやる。Defence Colonyを毎日掃除してくれるお兄ちゃんまで、いつの間にかいるではないか。本人は、新居で搬入された荷物をどこに置くか指示するだけだ。慶應で二人部屋から一人部屋に引っ越ししたときは、大変だったなーと、思い出してしまう。実は、Rituの机の下には、小生の巨大でやたらと重い段ボールが置いてあるのだが、それまで運んでしまったらしい。しばらくたって何かを引きずる音がしているので見てみると、小生の段ボールが元に戻されて行った。どうやら明日には、席が確定しそうだ。
昼は、南口の店へ行こう。1時20分ごろに外に出ると暑い。完全に元に戻っている。残念。でもウ○コにことは、とうぶん心配しないでよさそうだ。店に着くと、なんと階段の下まで並んでいるではないか。先日は、1時ごろにオフィスを出て、食べ終えたころに空いてきたので、今日は此の時間にしたのだが、うまくいかない。どこも1時前に店にはいるのが、いいらしい。下でSamosaとPakoraを買って帰ろうかと思ったが、Samosaを揚げている最中だというので、Eatopiaに行く。今日は、Non-vegetarian Thaliにした(Rs.150)。Paneer(チーズ)の代わりにチキン、Kofta(肉食感の野菜の団子)の代わりにマトンが入っている。Eatopiaに関しては、Vegetarianに軍配があがるというのが正直な感想である。
帰りは、露店街経由。Habitat Placeを出てから露店街に入るまでにRickshawがしつこくつきまとって来る。「昨日お前のことをマーケットで見た。乗っていけ」、「マーケットになんか行っていない」、「いや見た。インド門までRs.20でどうだ」、「前にお客がいるぞ」といったんは振り切るが、しばらくしてまたやってくる。「俺は歩くのが好きなのだ」、「でもインド門は遠いぞ。Rs.20だ」、「インド門には行かない」。また一度消えるが、露店街に入る寸前で現れる。こんどはRickshawを降りて、「よーく聞け。1KmあたりRs.1でいい」、「とにかく必要ない」、「おまえどこえ行くんだ。そっちの方角に行ったて何もないぞ」、「家へ帰る」、「家?そうか」と行ってHabitat Placeの方へ戻っていった。Habitat Placeで「家へ帰る」といっても、「どこだ。Defence Colonyだと30分かかるから乗っていけ」となっただろう。露店街に入るところで、そういったものだから、自分があのごたごた露店街を運転したくなかったにちがいない。
家に戻ると、また一人である。ここを訪ねる人たちと仲良くなろうなどという考えは、そもそも妄想だったようだ。挨拶することさえできやしない。
以下、仕事のメモ。
Energy Statistics Manualにしたがって、公表されているインドと日本のエネルギーバランス表を再構成してみる。両国ともエネルギー部門の高炉の行は空になっており、その分は鉄鋼部門の最終エネルギー消費として配分されている。消費されたエネルギーが転換部門、エネルギー部門、最終消費のどこに配分されるかはあまり問題ではない。詳細なエネルギー商品について、それを生産し、消費する活動が詳細に分割されていて、その部門間のエネルギーフローがバランスのとれた形で記述され、さらにエネルギー消費なのか非エネルギー消費なのかが明確に区分されていればよいのだ。その意味では産業連関表形式の方が、わかりやすいのではないかと思うが、明日産業連関形式への変換をして、その違いをもう一度整理しよう。
この表象の仕方は、CO2、SO2、NOxなどの排出量の計算にも関連しているはずだ。手元には、IEAのCO2 emission from fossil fuel combustionに関する資料がないので、IPCCのGuide lineを読んだ。鉄鋼部門については、生産プロセスでコークスの不完全燃焼によって発生する高炉ガス、転炉ガス(いずれもCOが主成分)の消費に関する排出は計算しないで、コークスが完全燃焼してすべてCO2になったものとして計算せよ、とある。コークス炉ガスも含めて、これらの副生ガスは、鉄鋼部門の外でも消費されるから、IPCC方式は、部門別排出量の計算には向いていない。また、排出削減政策としての部門別アプローチを議論するためにも、この方式は相応しくない。ただし、コークス、副生ガスのそれぞれについて完全燃焼した分だけを捉えようとすると、燃焼の仕方によって、コークスの排出係数を変動させるか、COとなった部分は、他のエネルギーへのfeedstockと考えて原料・燃料比率を操作するかのいずれかになるだろう。われわれのEIOでは、どうなっているか確認するために、日本にメールを送った。
エネルギーバランスに関する作業は、TERIのメンバーにやってもらうとして、IOにかかわる作業は、まず小生が行って、それをマニュアルとしてまとめ、TERIに伝授する。そのための作業も平行して開始する。
98-99のMake matrixでは、各部門の自家発電が計上されていなかったが、2003-04年表で計上されている。その数値のチェックのために、基礎資料による自家発電量の値と比べてみることが必要だ。そのためにGeneral Review 2005をダウンロードする。General Reviewは、公式には目次しか公表されていないのであるが、章毎にPDFファイルはアップロードしてあるので、推量でURLを指定して、全部ゲット。
TERIも引っ越し
08/10/15