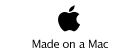Taj 多事
2008
5時半起床。昨晩も10時過ぎに30分間ほどの停電があった。停電の間に眠りこけてしまったので、解除とともに寝た。ストレッチなどをして6時半過ぎにシャワーを浴びに、バスルームに入る。その直後、ピンポーンとチャイムが鳴る。お向かいさんを迎えに来た車の運転手にちがいない。7時半頃またチャイム。それでも無視。8時過ぎには、鍵を持っているもう一人が現れて、ついに中に入ってきた。ちょうど歯を磨いてバスルームから出たところだったので、小生が依頼主かと勘違いされた。お向かいの部屋をノックしても、梨の礫。どうしちゃったんでしょうか。 おかげで運転手さんがチャイを一杯いれてくれた。大変美味しい。御馳走さまでした。冷蔵庫に牛乳はないけど、どうやって作ったんだ?
9時に家を出る。暑い。9/24にインドに着いて以来、雨は一度もない。今日も陸橋通りで、歩道のない大通りを怖々歩く。やはり、こう暑いと、少しでも早く着く方がよい。だったら乗っていけよとRickshawワーラーに言われそうであるが。
さて、Habitat Placeに向かって橋の右側は、ビニールテントの家々であった。今日は、左側を歩いているのだが、こちらはバラックというのだろうか、トタンやら木やらで囲われて、かろうじて家の形はなしている。よく見ると長屋のように真ん中に路地があり、住人が路地に出ている。バイク持ちもいるし、牛もうろついている。洗濯物は屋根の上に干すようで、屋根が吹き飛ばないようにレンガなどで重しもしてある。右側にくらべれば、少しは人間らしい暮らしができているようだ。つまり、橋の右と左でも目に見えてわかる格差がある。ここに住む子供たちも教育機会には恵まれていないだろう。車がラッシュの時間帯になれば、危険は承知で交差点に出かけて行き、「10ルピー」とやるにちがいない。それは、これらの家計にとって欠かすことにできない収入源にちがいない。右側の住人は、突風が吹けば住居を失うし、左側の住人だってモンスーンがきたら家ごとすっ飛ばされてしまうだろう。経済が順調にいっているときには、この人たちにもおこぼれが回ってくるのだろうが、経済が不調になったり、自然災害があれば、まっさきにこれら最貧の人たちが、立ち直れないほどの痛手を被ることになる。順調なときの分け前でさえ平等とはいないだろうが、逆風が吹いたときには一気に不平等度は拡大することは、これを見れば明らかだ。
今日もRituは来ないという。小生のためにどこか別の場所で仕事をしているのではないかと気になってしまう。それほど暇じゃないはずだけど。Rituグループは、NCAERとの共同プロジェクトの報告書をまとめるにしばらく時間がかかりそうだ。それが終わった段階でスムーズにこちらのプロジェクトが開始できるように準備を進めないといけない。それにしても、資料を広げられないのがなんとも痛い。
昼は、久しぶりにEatopiaでThaiカレーのコンボ(Rs.170)。どうみてもHabitat Placeの中の物価は高い。でも歩いて行ける範囲内でタイ料理を食べることのできるのは、ここだけだから我慢しよう。レシートももらえるし。お茶を入れてくれたり、郵便物を届けてくれるオジさんが、並んでいる。小生は、すでに席についていたのだが、あちらも気がついたようで、手を振ってあいさつする。ところがオジさん、自分が食べに来たのではなくて、大量のThaliをかついでどこかに行ってしまった。TERIの4Fで開催されている小さなシンポジウムのランチの買い出しのようだ。やはり、彼らここで食べてはいけないようだ。
6時過ぎにTERIを出て、またもや陸橋経由で家に戻る。この時間帯は車の帰宅ラッシュのようで、2カ所で大通りを横断するのだが、えらく時間を要してしまった。それにしても、この経路で帰るときには多くの牛に遭遇する。遭遇するというのも、あちらから細い歩道を歩いてくるとすれちがわないといけないのだ。絶対に現代日本でない事態である。ただ、初期のころの緊張感がなくなってきているのを感じる...
家に戻ると、お向かいさんは、いなくなってしまったようだ。ただ冷蔵庫には、昨日から置いてある買ったばかりの食パンが置いてけぼりになっている。また戻ってくるのだろうか。いくら冷蔵庫にいれてあるといっても、ズーットそのままにしておいたらすごいことになるぞ。
隣にも住人が居るではないか。顔も合わせていないのだけれど、どんな人だろう。小生が一人部屋にいるから、隣の人は、たとえ一人でも二人部屋だ。隣にはデスクもあるし、ラッキーだなー。
以下は、今日の仕事に関するメモ。
インドは、IEAにエネルギーバランスを報告していない。したがって、IEAが報告するエネルギーバランスは、IEAの独自推計である。2007年のIEA World Energy Outlookには、TERIの協力によって次の2点が改善されたとある。1) バイオ燃料の最終消費が、NSSOの家計調査とthe International Institute for Applied Systems Analysisを用いて家計、農業、サービスに配分され、さらに家計は農村部と都市部に分割された 2) 電力の産業別消費がより詳細に配分された。これらの貢献はRituグループによってなされた。
今回は、これに加えて、以下の4点を改善したいと考えている。1) 鉄鋼系ガスの発生と消費、2) 石油製品の振替と石油化学からの戻し原料、3) パルプ・紙製造から排出される黒液、4) セメント製造における石灰石起源のCO2を把握するために、石灰石のマテリアルバランスを作成。
今日まで、1)、2)がどのように不完全であるかを説明する資料を作ってきたが、その過程で日本がIEAに報告しているエネルギーバランスにも、IEAの定義に照らして不可解な点があることがわかった。
IEAマニュアルによれば、
-
1)鉄鋼生産で消費されたコークス、石炭、石油はエネルギー転換として記述
-
2)熱風炉に投入された高炉ガスはエネルギー部門消費として扱う
とある。
日本の総合エネルギー統計では、後者を鉄鋼部門の最終エネルギー消費とし扱っている。IEAに提出する際には、これらはエネルギー部門にある高炉ガスの行に転記すべきだと思うが、そうなっていない。エネルギー部門にある高炉ガスの行は、空である。
総合エネルギー統計を知らないIEAエネルギーバランスの利用者に誤解を招きかねないし、総合エネルギー統計は、IEAともEurostatとも異なる独自のフォーマットを採用しており、英文での解説もないようであるから、総合エネルギー統計を使えというわけにもいかないだろう。
橋のもう一方
08/10/14


橋の左側は、こんなバラック
長屋のようになっています